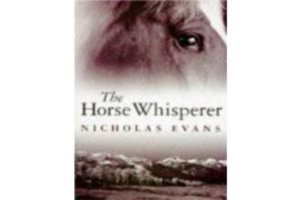百済の王子(5)
更新日: 2015-03-24
セーラが連れて行かれたところは、大きなわらぶき屋根の家だった。家の周りは土塀で囲まれ、門のところには二人見張りが立っていた。女はどうやら身分が高い人らしいとセーラはにらんだ。セーラが連れていかれたところは、馬小屋の隣にある、部屋だった。部屋とはいっても、床はなく、つちである。屋根はあるものの、屋根の下は隙間があり、外にいるのとたいして変わらない。ただ逃げようとすると、ドアがあるので、容易には逃げられない。リュックサックも取り上げられ、縛り上げられたまま、その部屋に放り入れられてた。男達が去り、一人にされると、セーラは自分の身に一体何が起こったのかを考えてみた。
タイムスリップしたとしても、一体いつの時代にタイムスリップしたのかさえ分からない。あの連中は日本人には違いない。女が羽衣のようなものを着ていたところを見ると、江戸時代ではなさそうだ。セーラの日本の歴史に関する知識はたかがしれていた。だからすべての知識を動員しても分からない。ただ天武天皇も知らなかったようだから、天武天皇の前の時代に違いない。そんなことを考えていると、おなかがすいたことを思い出した。昼チョコレートのかけらを食べたきり、昼ごはんも食べていない。何時ごろだろうと腕時計を見ようにも後ろでに縛られているので、見ることもできない。段々あたりは薄暗くなってきているところからみると、夕方だろう。日本の今の季節の日暮れって何時ごろだろうか。たぶん5時ごろだろう、そう見当をつけた。周りが暗くなると心細さが増してくる。このままここに閉じ込められて、餓死するのかしらと思うと、情けなくなってきた。ママはどうしているかしら?パパは?と家族のことが恋しくなる。「トム、助けに来てよ」と心の中で叫ぶと、涙が出てきて、頬をぬらした。その晩は誰も小屋に近づくものはなく、馬の鳴き声がときおり聞こえるくらいで、シーンとしていた。皆私のことを忘れたのかしらと半ば諦めていた頃、戸がいきなり開いて、あの女の家来の一人が、何やら手に握り飯のような物を持って入ってきた。「手が使えないと飯もくえないだろう」と言って、やっと縄を解いてくれた。
「ほら、食べろ」と出された握り飯をセーラは素早く奪い取って、口に頬張った。空腹だったので、マナーなんて考えてはいられなかった。玄米でできた固い握り飯だった。口にほうばると、口の横からぽろぽろと、ご飯が落ちる。それも構わず、一気に食べると、やっと落ち着いた。セーラが食べ終わるのを見て、あの女の家来が言った。
「明日の朝、額田王(ぬかだのおおきみ)様がお前に色々お聞きになりたいことがあるそうだ」
「額田王って、あの女の人のこと?」とセーラが聞くと、
「そうだ。美しい方じゃろう」
「ふうん。そういう名前の人なの」
セーラには額田王と言われても、誰のことか分からなかった。それに美人かどうかも良く分からなかった。卵のようなうりざね顔に下膨れしたような頬、そして色は白く目はほっそりしていて、口はおちょぼ口。セーラの思う美人とは程遠かったが、肌のきれいな人だったことは確かだった。
男は、「逃げるなんて事を、考えるなよ。そんなことをしたら、すぐに殺すからな」と恐ろしいことを言って、出て行った。
セーラも逃げることなんて考えていない。だって、どこにどう逃げろというのだろう。男のくれた握り飯で空腹の虫はおさまったが、固いご飯だったので、何度もかまなければいけなかった。そう言えば昔の人は食べ物が固くてよくかまなければいけなかったので、あごが発達していたと聞いたことがある。今日出会った連中を思い浮かべてもあごの細い者はいなかったように思う。こんなことを考える余裕ができたのは、少し空腹を満たしたからだろう。夜になると段々冷え込んできて、肌寒く、腕をさすって、少しでも体をあたためようと、胎児のように体を丸めて寝転がっていると、疲れがでたのか、セーラは少しうつらうつらしたようだった。次に目を覚ましたときは、朝の光が屋根の隙間から差し込んでいた。
著作権所有者:久保田満里子