小説版バイリンガル子育て 第18話 『運命という名の船に乗って 後編』
更新日: 2010-07-22
親父が危篤状態に陥ったと、叔母から電話があったのは12月26日の早朝だった。
前日のクリスマスの夜、僕は草サッカーのチームメイト二人と居酒屋で飲んでいた。1999年に僕が中学の同級生と作った草サッカーチームで、ほとんどのメンバーをインターネット上で募集して集めた年齢も職業もバラバラのチームだ。そこから始めてもう10年、今ではすっかり親友になった。気の合う仲間とのお酒は楽しい。浴びるほど飲んで家に帰ったのは午前4時前だったと思う。
「死んだら連絡して」そう言って僕は電話を切った。そこから再び眠りにつくまでの間、数秒だったのか数分だったのかわからないが、今でも覚えているのは、酒に呑まれてさんざん人に迷惑をかけ死んでいく男の息子が泥酔していて親父の死に目に会えなかったというのは、皮肉で面白いと思ったこと、病気の体に鞭打って一生懸命僕のために働いてくれたお母さんの死に目に会えなかったのに、そんなお母さんに辛い思いをさせていた親父が死に際に息子に来てもらえるのは不公平だと思ったこと、半年ほど前から何を言っても無気力な返事しか返ってこなくて、その時点で「親父はもう死んでいるんだ」と彼女に話して泣いたことを思い出し、その時に別れは終っていると思ったこと、そして、親の死に目に会えたかもしれないのに、会わない選択をした僕のことを考えている間に眠りに落ちた。
数時間後、叔母から親父が死んだという連絡があった。僕は店を開けて一通りの仕事をして、午後6時に店を閉めて親父の所へ向かった。とうとう本当に死んでしまったという気持ちと、やっと死んでくれたという気持ちが頭をぐるぐる回っていた。
僕がまだ赤ん坊の頃、僕の家では親父が毎晩のように友達を呼んでマージャンをしていた。親父たちがマージャンをしている隣に、コタツをひっくり返して、そこにシーツを巻きつけてハンモックのようなものを作り、赤ん坊の僕が置かれていた。タバコの煙が途切れることのないその部屋で僕は育てられた。僕が喘息にならなかったのは奇跡に近いと思っている。そんな環境で育ったので、幼稚園の時にはマージャンを覚えていた。そして中学の時に友達がマージャンに興味を持ち出し、付き合いでやったりしたが全く面白いとは思わなかった。
僕が幼稚園児のころには、夕食中によくお皿が宙を舞った。台所にいる母に向かって、酔っ払った親父が「こんな不味いもの食えるか」と言って皿を投げつけるのだ。僕は母の前に立ち、「やめろーっ」と両手を広げて立っていた。
僕が小学校4年生の時には、泥酔して家の階段から転げ落ちて玄関の戸にぶつかり、ガラスが割れて血だらけになっていた。病院に行けと言う母に「今日は休みだから嫌だ」と言い残し、親父はオートレースに行った。翌日には仕事だったので休んで病院に行った。僕が学校から帰ると、親父が全身を固定させられて寝ていた。首の骨が折れていて、あと少しで死んでいたそうだ。
こんな最低な父親だったのだが、母は「お父さんを嫌いにならないでね」といつも言っていた。
僕がオーストラリアに留学してすぐに母が亡くなった。これで親父との縁も切れると思ったのだが、「お父さんを嫌いにならないでね」という母の言葉が引っかかる。なぜ母はそんなことを言ったのだろうか。その頃、親父の酒癖は昔よりは多少マシになり、暴れたりはしなくなっていた。僕は親父のことを好きになろうと努力をすることにした。
オーストラリアから帰るたびに一緒に酒を飲んだりした。いきつけの寿司屋やクラブに僕を連れて行き、僕を自慢する親父はとても嬉しそうだった。こうして一緒に飲むようになると、親父の良さもわかるようになってきた。親父はよく気が利くし、根本的には優しい人だった。
今にして思えば、母があそこまでされても「お父さんを嫌いにならないでね」と言い続けてきたのは、きっと僕に親を恨むことをさせたくなかったのと、親父にチャンスをあげたかったのだと思う。親父は晩年、僕と二人で酒を飲むと、時折「全部あいつのおかげだ」と母に感謝をしていた。僕がグレなかったのも、親父と最後はいい関係になれたのも全部お母さんのおかげだと思う。
数年前に親父が血を吐いて救急車で病院に運ばれた。なんとか一命は取り留めたが、僕の顔を見てもヘラヘラ笑うだけの赤ん坊のようになってしまった。当然自分で食べることもトイレもできない。医者はもう元には戻らないのでと、介護施設を紹介してくれた。僕は納得が行かなかったので、自分でなんとかしようと毎日親父のところに見舞いに行って、僕が赤ん坊の頃からの写真を少しずつ見せて「これ覚えてる?お父さんとお母さんが僕を動物園に連れて行ってくれた写真だよ」などと説明をした。赤ちゃんになってしまったのなら、赤ちゃんからやり直せば記憶が戻ると思ったのだ。親父は「アー、ウー」と言いながら写真を見ていた。
それから5日くらい経ったある日、また僕が見舞いに行くと、親父はベッドの上で体を起こしていた。目が合った瞬間にこれまでの目じゃないと思った。「おお、正彦」親父の記憶は奇跡的に戻ったのだ。
それからは毎年1回くらい血を吐いて入院というのが繰り返された。親父の場合、酒のせいで肝硬変になり、本来肝臓に流れるべき血流が食道の静脈に流れることにより瘤状の膨らみができて、それが破裂して出血していた。毎回呼ばれる度に「覚悟はしておいてください」と医者に言われ、その度にそれなりの覚悟を決めるものの、幸か不幸かなんとか一命を取り留め、挙句病院を脱走して家に戻ってきたりするのだ。
親父の体のことを心配している僕の精神状態の方が先に変になりそうだった。実際、寿命は何年かは縮まったと思う。
僕が斎場に着くと、既に叔父、叔母、祖母が来ていた。生前の親父の希望通りに、お通夜も葬式もせずに火葬だけすることにした。入院してからの親父は酒が抜けて、体は弱っていたけど、思考はできたようだった。叔母が看護婦さんから聞いた話では、死ぬまでの最後の数日間は毎日穏やかな顔で、新太郎と由莉杏の写真を見ながら、微笑んでいたのだと言う。その時僕は、彼女が親父に手紙を書いてくれていたことを知った。由莉杏という名前を付けてくれてありがとうという手紙と、新太郎が由莉杏を抱っこしている写真、新太郎が書いた家族の絵を送ってくれていたようだ。彼女が送ってくれた手紙と写真のおかげで親父は穏やかに最期を迎えられたと思う。

その夜は、徹夜で最期の酒を親父と飲んで、翌日火葬場に行った。親父の体が燃やされている間、外に出てみると富士山が綺麗に見えた。雲ひとつ無い青空の下、日本一の富士山のふもとで煙になった親父。新太郎と由莉杏、二人の孫に名前を付けるのが親父の生まれた理由だったのかも知れない。天に昇る途中でこっちを見て、「もう十分だ。これからはお前の家族のことだけ考えろよ」親父がそう言っている気がした。(つづく)

※読者の方からの質問や応援メッセージ大歓迎です。コメントお待ちしております。
日本初の本格英語子育てマニュアル→子どもがバイリンガルになる英語子育てマニュアル
僕の会社です→メモリアルCDショップ音吉プレミアム
書籍化された僕のブログ→イタリア人は日本のアイドルが好きっ
英語で日本のサブカルチャーについて書いているブログ→ROAD TO OTAKU



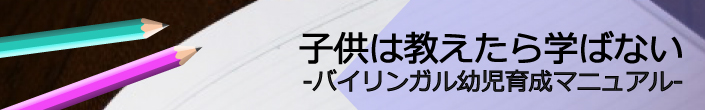









コメント