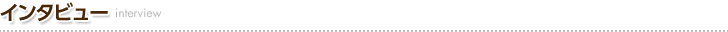ゆみ・うみうまれさんインタビュー(後編)
ソロダンス『En Trnce』 作品への想いとメッセージ
2010年3月4日掲載
メルボルン在住で国際的に活躍されているダンサー、ゆみ・うみうまれさん。
今回の後編では、メルボルンプレミアム公演が高評を得たソロダンス作品『En Trnce』を中心にお話を伺いました。
また、ゆみさんからメルボルンに住む方、創作活動をしている方にメッセージが!
--『En Trnce』 を観させて頂きました。日本のテイストが結構入っていたように感じましたが、海外で公演する際に日本のテイストを出していこうなどの意識はされていますか?
今回の作品に関しては、意識して日本の物を入れようとしたつもりはないですが、確かに言われてみると演出の中で日本語を意識的に使ったとかありましたね。
自分が日本人なので、いきなりシェイクスピアをやる訳にはいかないので。海外にいるから日本を意識したというよりは、自分が日本人だから結果としてそのエッセンスが入ってしまうという部分はあると思います。
ドラマターグ(※)で今回演出の手伝いをしてくれた人が、日本的な美しさや演出法も判っていたので、オーストラリア人が観ても判りやすいように意図したということはあります。
昔は、自分の中の日本的な感覚のみを持ちこんで作品を創っていたこともあり、オーストラリアの観客にはきょとんとされたり、特に舞踏などは、ただゆっくり動いるだけだと思われたりしました。
西洋系の人は、ストーリーや論理が好きな人が多いので、ロジックを取り入れた抽象や、物語風にするなどちょっとアレンジして試行錯誤しながら作品を創っています。
確かに、オーストラリアに移住して作品を創りながら、現地の人たちが共鳴できるように作品のスタイルを変えていく作業は、知らないうちにしてきたと思います。
日本の舞台の中で抽象的なことは受け入れられやすく、こっちの人は論理的に説明したがる印象があります。
私はその論理性を学ぼうとそれを積極的に作品創りに取り入れてもおりますが、その反面、直感的、肉体的なこと、
例えば言霊とか、どこに行って演るにしても、どの言葉でしゃべっても、魂というかスピリットが有ると思うので、そのあたりのことも作品に取り入れます。
言葉についても、日本語を話す時の自分の肉体、英語を話す時の自分の肉体について考えたりします。
(今回の演出の中で)文字が映像として上から落ちて来たり、カラオケがあったり、日本人だからということより、自分がいる両方の国を差別なくとらえていきたいと考えてました。
今回の創作チームの日本人はわたしを含め2人、インドネシア出身のアーティストも含むその他のアーティストは、日本になじみのない人達も含まれていましたが、そういった人たちが関わってくれることで良いミックスが生まれたと思います。
--今回の作品はどのような制作過程だったのですか?
2007年から2年半のゆっくりした過程で作品として完成させました。
舞台で使う映像を集めるにも日本に行って撮影したり、それを映像作家がアーティスティックに編集したり、音も撮影したものや、作曲したものを編集したり、様々なことを並行した作業だったので時間はかかりました。
例えば、パンクメデューサ(今回の作品の一部)というのも、音楽は2007年に作ったんですけど、ショーイング(制作過程を一部観せる公演)には出さなくて、1度棚にしまったようなものでした。
その時は音がこじんまりしていて軽かったので、もうちょっとヘビメタみたいにするよう作曲家に言ったら、イメージ通りに創ってくれて、その曲が今度は映像作家のほうに良いインスピレーション、良いアイデアを与えることとなり、いろんなコラボレーションが偶発的に生まれました。
そういうたくさんのことが統合されて作品が生まれ、後から考えるといろんな面でラッキーだったなと思います。
--作品の中で何回か衣装替えがあって、その時に衣装がこすれる音や、ジッパーのあがる音が静まった会場内に響いて、個人的にかっこいいなと感じたのですが、それらは演出の一部だったのですか?
サイレンスというか、それは日本的な美意識かもしれませんね。
何でも「出していこう、出していこう」という突出するものに注目するのだけでなくて、引いてゆくもの、それが沈黙だったり、そこに生まれる影だったりとか、そういうささやかな瞬間を突出する狭間に創りに観客を引き込んでゆくことに喜びを感じます。
出すばかりだと客は引きますが、こちらが引くと今度は向こうが舞台に引き込まれてゆく。それはいつも私は考えています。
音が全くないところに、ちょっとした音があると、それがシャープに聞こえることがありますよね。
騒音のような曲があり、その後急に静けさがあったり。
そこで舞台から客をやくざのようににらみつけたり。
--そのようなことは意図的にされていることですか? それとも偶発的にでてきたことですか?
創作の流れの中で生まれて来たことですが、心理的な、また詩的な探索から生まれることですよね。
こうしようとか、この意図でやろうとか、ある程度は意図して創作していくうちに、偶然も生まれ、そこから洗練されていくことはありますよね。
「そうしなくちゃ」というより、「そうなっていった」という感じですね。
--同じ作品を日本でやるときと、海外でやるときで内容は変えていますか?
「舞踏キャバレエ」のシリーズを公演していたことがあって、その代表作に日本公演した『脱色カルチベーション!!』、オーストラリア公演をした『DsSHOKU HOR!!』というものがあります。“Ds Shoku”と色を抜く“脱色”を掛けていたんですけど、オーストラリアでは「日本人がエキゾチックに見られること」を、逆に日本にでは「西洋人がエキゾチック化される」現象を題材に、舞踏とキャバレーを掛け合わせて創りました。
『脱色カルチベーション!!』は大阪の劇団「GUMBO」というグループというハチャメチャな元気の良い劇団とのコラボレーションだったのですが、日本人が「V」の発音をできにくいと言う現実を日本人の生真面目さと掛け合わせて、「V、V、V」という発音を彼らが必死で繰り返していくうちに口から血が出てくる、そういうブラックユーモアみたいなことをシーンにしたり、様々なクロスカルチャーの現象を面白おかしくキャバレエのエンターテインメント性を取り入れて創りました。
その時の謳い文句が「ショックと癒しがクロスする」。文化交流にショック(カルチャーショック)を受けながらも癒される、みたいな。またダークユーモアを使いながら、その作品は「カルチャー」をメインテーマにしました。
公演する国へ、ただ作品を持っていくだけでは意味がないので、その国の人が受け入れやすいようにアレンジをしています。
東ヨーロッパとかエジンバラでの公演したりするので、国によって内容は変わるけど、それはこっちが提示して変える物ではないので、やっぱり演劇的なものになった場合は言葉だとかニュアンスを変えていかないと、みんながついて来れなかったりするので、今回の『En Trnce』の中でも英語でしゃべらず、日本語でしゃべるシーンもあったり(演出のなかにある)カラオケなんかはちょっと古い曲で、日本人はみんな知っているので、日本に行ったら使わないかもしれないなど、公演先の国に合わせて変えていく可能性はあると思います。
他の作品で『バレスクアワー』という作品は、言葉のないダンスの多い作品なので、内容はそのままでやりますね。
--『En Trnce』 を観る人たちに、どのように観てもらいたいですか?
観る人によっていろんな感じ方があって、いろんな感想があると思いますが、面白かったって言う人もいれば、訳わからなかったけど引きつけられたっていう人もいるし、あんまり頭で考えずに“感じて”もらえればいいかなと思います。
今回は6つのシーンがあって、観る人にとってはどうしてもストーリーを追ってしまったり、その意味を考えたりする場合もあるかと思うんですけど、観る側は、作品を観て聞いて、パフォーマーと一緒になって感じて、どこかでセンス、感覚が、呼び起こされればいいかなって思いますね。
ある批評の中で、「内蔵や体に響いてくるものがあった」のようなことを書いてあったのがありました。感情をあまり論理化人せず(人間ついつい論理的結論を求めてしまうけど)感覚的に観てもらえたら幸いです。

(Photo by Jeff Busby) (Photo by Jeff Busby)
--作品を創る際、どのような方法で作品を創っていますか? またどのような方法でアイデアを膨らませて形にしていきますか?
どの分野でも創作するときは同じだと思いますが、何もない状態から形にすることは大変なことですよね。だからといって、それをもったいぶらずに、とにかくそれアイデアをノートに書き出したり、実際に踊ってみたりして、まず初めに形にしてしまう。
形にすることによって、白だったのが赤の方が良かった、などが具体的に見えてくる。形の無いところだけで考えてしまうと、もう抽象の中で、頭がうにゅうにゅしちゃうから、それはなるべく避けて、具体化します。
今回もたくさんシーンは創っていたんだけど、それからがもっと大変で、形が有りすぎてどう溶かしていいか判らないというか、どれがいいか判らなくなっていしまって、
その過程の中で自分でも、わざと未知の世界にわざと投げ込むというか、全部を計算し尽くしてしまうとすごくつまらない。自分でもつまらないし、お客さんもつまらないだろうから、自分でそこでリスクを踏むということですよね。
そこで、自分で本当にリスクを踏めるかというところが、厳しい選択になります。
今回もずっと通し稽古ができなくて、ゲネプロまで全く一回も通しができなくて、シーンごとにぶつぶつ切れた状態でリハーサルをしていたんだけど、ゲネプロで全部通したことで、ようやく全部が見えて来てという状態でした。
また未知な部分を残す創作過程で、わざと判らないところを残しておくことも悪い事ではないと思うけど、余りに未知すぎるとある種の不安感がでてきてしまうので難しいところです。
ある程度ポイントを押さえつつ、未知で判らない部分があることも良いと思う。
--作品を創っていて、不安になったり、これって本当に面白いのかなと悩んだりする時どうやって切り抜けていますか?
やっぱりそういう時は、クリエイティブ・チームの人からのフィードバックや、その反応を見て修正したり、また深く考え直したりしますね。
自分ひとりのソロだと独りよがりの細かい世界に入りがちなので、他の人と働いて客観性をもてるようにします。
自分の世界は掘り下げながら、客観的にアドバイスをくれる人にフィードバックをもらいます。
今回は自分の事を良く理解している、ドラマトゥルグ(※)の人が参加してくれとても助かりました。
自分の世界でウジウジしなくて済むし、初日になるまで私も創り出した作品がどのようにお客さんが反応するのかを考えるのはやっぱりすごく不安だし、
みんな、「なんじゃこりゃ」って思って帰るんじゃないかとか、客が来ないんじゃないかとか、チケット売れないんじゃないかとか、初日前までの不安はつきません。
でも、そういう風に考え込んだり、悩みだすと、そちらの方にエネルギーを使いきってしまうので、今回はそういうことにとらわれず、自分の作品を信じました。
いい部分であきらめました。
--ソロで踊るのと、集団で踊るのは、どっちが好きですか?
全くソロでの本公演は今回が初めてで、正直すごく怖かったんですけど、やってみて意外と「できてしまった!」と言う感じです。
でもそれは素晴らしい創作チームに恵まれていたという事が大きくて、今回は本当にラッキーでした。
例えば、今回関わってくれた様々なアーティストの創りだす映像やインスタレーション。映像は映像で私と踊ってくれているような、また、インスタレーションも一緒になって踊ってくれるし、照明や音楽も舞台に色彩を加え私自身にフィードしてくれるから一人っていうのに対する不安はなかったですね。
郡舞でやるときは郡舞の面白さと大変さっていうのがあって。ソロでも集団でもそれは両方にありますよね。
それは生きていくのと一緒ですよね。一人でだらだら生きていいくのは簡単だし、それなりのすごく簡単な方法はあるけれど、またうまく人の助けをかり共生していくことで学べることは多いと思います。
やっぱり人とシェアする部分で大変な部分はあっても、一人ではけっして出来ない力強さを群舞には出していけるというようなことはあります。
大駱駝艦などで大きなステージで20人が走り回って踊っているのは、すごくスペクタクルだったと思います。
--今後の展開としてソロと群舞どっちをやっていきたいですか?
両方できたらいいですね。過去何度も公演している『バーレスクアワー』のように、舞台ではソロでも、たくさんのパフォーマーが順番でソロを踊っていく、そういうのはやりやすいし、楽しいですよね。
舞台を踏む人間もたくさんいると、公演ツアーでも他の街に行く時も出演者やスタッフがいて楽しいしけど、ソロだと楽屋は一人だからつまらないなとか。
今後の展開は、チームやスタッフの人たちによって変わるし、今回の作品は出来て間もないので、将来の公演ツアーでまたいろんな事が見えてくると思います。
--自分自身をパフォーマーだと思いますか、演出家だと思いますか?
パフォーマーの方だと思う。
最近は4、5年前位から演出や振付けをやっていて、去年沖縄などでも振付け作品の公演作品に関わり、自分はすごくそういうのにも興味があるし、これからもやってみたいと思う。ただ自分は出たがりだから、出ます。それが基本ですね。見ていても体が動くし、自分の考えた振付けや演出をやってもらっていても体が歯痒くなっちゃうから、自分がやってみるとどうできるかって、気がついたら自分のほうが動いていたりしますね。
今のところ自分が出演するほうにエネルギーを使っていることが多いですが、将来は変わっていくでしょう。
--メルボルンに訪れようとしている人、来ようとしている人、そして創作している人に対してメッセージをお願いします。
メルボルンはアーティスティックな街で、創作的なことのできる環境に恵まれていると思います。
また風土がオープンなので、いろいろなことが深く掘り下げられることができる場所だと思っています。
自分を深い部分で考えることができる、メルボルンはそういうチャンスを与えてくれる場所だと思う。
それはもちろん、黙って受動的に待つだけではなく、自分から動いてアクティブに活動しないと何もクリエイトできないでしょうが。
オーストラリアの風土、土地には、すごく深いスピリットのようなものを感じます。オーストラリアに古代から残っているアボリジニの力というか、土地そのもののパワーを感じるところがあります。また、メルボルンなどは白人中心ではない多国籍文化の社会なので、いろいろ学ぶことの多いところです。
メルボルンに限らず、オーストラリアの自然の力の強さはいつも感じます。
クリエイティブなことをし続けたい人に対して、アートだけをし続けることは精神的にも経済的にも大変なコミットメントだと思うけど、真実というか、自分や人間の持つ深い部分のようなものを追求することに集中すると、常に新しい発見が出てくるのではないかと思います。
--ありがとうございました。
(Photo by Jeff Busby)
ゆみ・うみうまれさん ホームページ
http://yumi.com.au
【2010年予定】
2月 「The Burlesque Hour」キャンベラ、アデレード公演ツアー
3月 「Salon de Dance」メルボルン公演
4月・5月 舞踏インテンシヴ・ワークショップ(ダンスハウス)
5月 「Trans-Mute」 メルボルン大学ワークショップ公演、振り付け・監修
6月・7月 「Zero Zero」 デヴェロップメント、公演@インドネシア、マレーシア、日本
8月 「The Burlesque Hour」ヨーロッパ公演ツアー
9月 アリススプリング、デザーと(砂漠)フェスティバル振り付けワークショップ
10月 「EnTrance」リズモア、ブリスベン公演ツアー
11月 「Zero Zero」マラッカ・フェスティバル参加
(※)ドラマトゥルグ/ドラマトゥーグ
舞台において、演出家の相談役などをする人。
日本ではあまり浸透していないが、ドイツでは18世紀頃から職業として成立している。
ドイツでも公演やフェスティバルの企画に関わるプロデューサー的な役割を担う者もいれば、かぎりなく劇作家に近い仕事をする人など、解釈はさまざま。