【対談1】 「日本人ミュージシャンの挑戦状」
MachPelican中村氏とTheWellingtons浅野氏
2011年6月13日掲載
Staff Solutions Australia × GO豪メルボルン特別企画 「対談」
今回の対談ではMach Pelican 中村氏(ボーカル×ギター)とThe Wellingtons 浅野氏(ギター)に「日本人ミュージシャンの挑戦状」と題し、これまでの音楽生活の振り返り、またこれからの未来について熱く語っていただきました。
2週連続(2011年6月13日、21日)に渡ってお送りする「対談」。
今週のテーマは「日本発-オーストラリア経由-世界行き」。
■対談者紹介
中村 圭良(Keisuke Nakamura)
<PROFILE>
1996年に来豪。日本人3人組によるバンド、Mach Pelicanのギター・ボーカル。
世界的なミュージシャンBuzzcocks、Radio Birdman, Rancid、Guitar wolf、ゆらゆら帝国、などとも帯同。
Mach Pelican
1996年。パースの日本人学生、Keisuke Nakamura (Guitar/Vocals)、Atsushi Omori(Bass/Vocals)、Toshi Maeda (Drums/Vocals)のメンバーにより結成されたPunk Rockバンド。1998年にメルボルンへ活動の拠点を移し、以降2007年の解散までに800ステージ以上のライブを行う。解散から4年が経った今も尚、オーストラリア人の熱狂的ファンから支持される伝説の日本人Punk Rockバンド。
■Mach Pelican Myspace
http://www.myspace.com/machpelican2005
■Mach Pelican Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mach_Pelican
浅野 浩治(Koji Asano)
<PROFILE>
2001年に来豪。ローカル音楽会社にてセールスマネージャーとして6年間勤務。現在はローカル企業でリサーチャーとして勤務。主に日本企業の株価動向の調査・報告業務を行っている。ビジネスマンとしての顔を持つ一方で、オーストラリアのパワーポップバンド‘The Wellingtons’のギタリストとしても精力的に活動し、日本、アメリカ、イギリスなどでもCDをリリースしている。
The Wellingtons
メルボルンを拠点に活躍するポップ&ロックバンド。メンバーはZac(vocals & guitars)、Kate(bass & vocals)、Koji(guitar)、Anna(keys)、Gustav(drum)の5人。オーストラリアでのCDリリースのほか、ライブハウスでの演奏を中心に、UKやスペイン、日本でもCDリリースおよび、ライブツアーも精力的に行っている。7月6日には日本でニューアルバム「In Transit」のリリースが決定。
逆輸入バンドとして今日本でも注目のアーティスト。
■The Wellingtons Myspace
http://www.myspace.com/thewellingtonsmusic
■The Wellingtons インタビュー記事
http://www.gogomelbourne.com.au/interview/entertain/2028.html
■Tower Records Online
http://tower.jp/item/2882114
■浅野氏による音楽情報コラム【Just Australia】はこちら
オーストラリアに来たきっかけ
中村)1996年の話なんですけど、最初は音楽を求めて来たわけではなく、海外で大学にいくという目的のために来たんです。
でも実はその目的は果たしていないんですよね。始め語学学校に半年行って、そこでドラムのトシくんに出会っちゃったんです。
1~2か月後、トシくんが移った学校にベースのあつしがいて、そこで2人がバンドを組むことになり、僕にも声をかけてくれて始まったんです。
浅野)語学学校にいた時から音楽の話になりました?
中村)もちろん、そうですね。
浅野)やっぱり好きな音楽とか共通ですよね。
中村)トシくん自体がものすごくRamonesが好きだったみたいで。もともと日本ではグランジのカバーバンドみたいなものをやっていたんですけど、RamonesのCDもいくつか持って来ていることを言ったら、「Ramones聴くやつ珍しいよ!」なんて話しが盛り上がっちゃったんです。
それがバンドの始まりですね。
浅野)まさか革ジャンは着てなかったですよね?(笑)
中村)着てないです(笑) その時は僕が18歳で、トシくんが2つ上くらいでまだ若くてピチピチだったもんで。
浅野さんのバンド結成のきっかけはなんだったんですか?
浅野)2001年にオーストラリアに来ました。僕はもともと音楽をやりに来たんです。英語と音楽を。
昔イギリスに行って1か月くらい交換留学をしたのですが、それをきっかけにもっと英語を身につけたいなぁと思って。
本当はイギリスでも良かったんです。結局はビザが取りやすかったのでオーストラリアに決めました。どこの都市で音楽が盛んなのか、ネットで調べると、どうやらシドニーかメルボルンが盛んだとのことで。
更にメルボルン在住の人たちのサイトなどを見ていると、みんな「メルボルンがいい!」って言っていたのでメルボルンに来ました。
それから日本にいるうちから、メルバンドというメルボルンでバンドメンバーを募集するサイトにバンドやらないか、と書き込みをしたんです。英語全くできなかったんですけどね。
すると、つたない英語で書いた募集でも2件くらい返事が来たんです。
メルボルン来たら会おうって。結果その出会いがきっかけとなり、バンドを組むことになったんです。
中村)へ~そんなのあるんだ。これから次のバンド、それで探そうかな(笑)
浅野)そんなの使わなくてもマッペリのコミュニティなら見つかるでしょ(笑)
活動拠点
浅野)そういえばメルボルンへ来る前はパースで音楽活動されていたんですよね?
中村)そうですね。パースの音楽シーン自体小さいということもありますが、当時のパースで日本人バンドなんて僕ら以外いなかったんじゃないかな?僕らは学生だったんですけど、ライブばっかりやってましたよ。
浅野)確かにパース出身のバンドってあまり聞かないですもんね。
中村)有名なバンドといえばEskimo JoeとかJebediah(ジェベダイア)。
当時は彼らと一緒にやってたんです。Eskimo Joeなんて僕らのオープニングバンドだったんですよ。それがいつのまにかものすごい売れてました。(笑)
98年に出した1stアルバムのLaunchではEskimo Joeが前座やってくれました。今じゃビックリですよ(笑) Eskimo Joeのドラマーがトシくんのドラムキット壊して、トシくん怒ったりしてましたよ。
浅野)今なら余裕で弁償してくれそうですけどね(笑)
中村)今じゃオーストラリアのトップアーティストですからね。
浅野)Jebediahは最近また復活してアルバム出したみたいですね。
中村)ボーカルがすごいヒット曲出したんですよね。Bob Evans。ドラマの主題歌とか作ってたし。あのバンドが結構きっかけだったんですよね。今ほどは有名ではなかったけど、その当時すでにメジャーのSONYのMurmurと契約していたんで。一緒にライブをやるってなった時は嬉しかったですね。
でも小さな街だから、年に100回もライブしてると飽きられちゃって(笑)だからメルボルンへ来ました。
浅野)そんなことないでしょ(笑)
メルボルンへ
中村)メルボルンへはツアーで来たんです。
でもツアー途中に資金が尽きて、そのまま住み着いちゃったって感じです。ただ既にリカバリーというテレビのショー出演なども決まっていたので、その勢いで拠点を移すことに決めたんです。
今考えるとパースという小さな街でスタートしたことが良かったんだと思いますね。
パースに来るビッグネームのバンドのサポートのオファーが突然舞い込んできたりして。だからBLINK182とかHenry Rollinsとかもその時代にサポートしたりしました。MXPXとかも。
浅野)ええ~!いいなぁ。
中村)だから片田舎でバンドをやるっていうのも逆にいいかもしれません。皆さん、パースおすすめですよ!今はどうかわからないですけど(笑)
メルボルンから世界へ
浅野)僕はメルボルンから出たことが無いんですよ。メルボルンで4~5個のバンドを1~2年ずつやって、一番活発にやっていたのがThe Wellingtonsで、このバンドを始めてから初めて音源を出したり海外ツアーに行ったりするようになりました。
前回のツアーでは日本、イギリス、スペイン、アメリカ、カナダに行きました。
僕は仕事の都合もあってアメリカ・カナダには帯同できなかったんですけどね。
中村)ヨーロッパはどうでした?
浅野)イギリスはコネクションも弱かったので、5人とか10人のところで小さくライブをしたり。一方でスペインではPOP好きの集まる、かなり大きなところでやらせてもらいました。
中村)スペインはラテン系の人だからかなり音楽も盛んですよね。
浅野)そうそう、色んなバンド来ますよね。日本と近いところが多いかも。英語わかってないんだけどノリノリみたいな。
中村)日本っぽいポップパンクバンドなんかもスペインには結構いるんですよね。パワーポップも多いですよね。
浅野)そうそう。それ専門のレーベルなんかもありますからね。ヨーロッパは結構行きましたか?
中村)ヨーロッパは1回だけです。だけど23公演くらいしました。ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オーストリア、スイスです。
浅野)そんだけ色んな国に行って、オーガナイズは誰がしてくれたんですか?
中村)ティーンエイジヘッドっていうプロモーション会社です。
ヨーロッパって国同士が隣接し行き来しやすいこともあり、バンドもツアーを周りやすいんですよね。だからそういった活動をサポートするビジネスなんかもしっかりしてるんです。
アメリカのバンドとオーストラリアをツアーしたときに、この会社のことを教えてもらい、問い合わせたんです。
車も機材も手配してくれ、おまけに運転手つきでヨーロッパを回ったんです。だからすごく楽だったんですけど、泊まる場所が・・・。ライブハウス上のカビ臭い屋根裏部屋とか、バーのオーナーの家とかもありました。
ヨーロッパって文化が違うから、かなりカルチャーショックでしたのを今でも覚えています。アムステルダムとか特に。
浅野)何がそんなに違うんですか?
中村)いきなりおねーちゃんがいっぱい・・・ ※自粛
音楽シーンにおける日本とオーストラリアの違い
編集部)実際色んな国を回ってみて、その場所・時々によってレスポンスは異なりますか?
中村)異なりますね。やっぱり国ではなくて、そこにどれだけその音楽が好きな人が集まるかによって違いますね。
浅野)あと事前に期待を持ってくれている人がいると、気分がものすごい高まるし、自分たちとお客さんとの相互作用で熱いライブになりますよね。スペインとか日本とか、特に。
中村)そうそう、日本とオーストラリアの違いってそこなんですよね。例えば日本の音楽シーンってすごく細分化されていて、ジャンル毎にライブやイベントがありますよね。
浅野)あぁ、ライブハウスもそうだし、レーベルやお客さんもそれ専門になりますもんね。
中村)そう、だから日本に行くと、同じ系統のバンドとばっかりガッチリライブをやるということが多いです。
日本のバンドがオーストラリアでツアーして驚くのが、色んなバンドと一緒に出演することが多いということ。
だからメタルのイベントにひょっこり入ったりすることも。
でもそれって面白いですよね。
他にも日本ではありえないオーストラリア特有のものって、ライブを見に来る人じゃなくて、普通にパブに飲みに来てる人が見れるじゃないですか。
浅野)その手軽さがいいですよね。ライブ見るのも安いし。バンド側も楽ですよね。日本なんてどこのライブハウス借りるのも20〜30万かかっちゃいますもんね。
中村)バンドがチケット売らないといけないしね。その点、僕ら最初のライブでギャラが出たことにビックリしました。小銭程度でしたけど、その瞬間すごく覚えてます。これってプロになったってことかな?!って。
浅野)いろいろカルチャーショックってありますよね。スタジオ行ったときもビックリしませんでした?なんだこのただの部屋!って(笑) マイクがあるだけで、防音もまったくないし、お化け屋敷みたいに壁こわれてたり。
中村)ははは(笑) こっちはマイクの静電気とかも抜かないから、最初から最後までしびれっぱなしとかもね。
浅野)日本は練習するのには恵まれてますよね。スタジオなんて全部そろって1時間1000円とかでやれますよね。こっちなんて5時間パックとかになっちゃいますもんね。
中村)日本だったらライブハウスも全部機材があるから、それが楽ですね。たぶんそれって日本はみんな電車でライブしにいったりするからですよね。こっちは最初不便だなと思ったけど、逆に毎回同じ機材でやれるから、同じ音は作りやすいかな。
浅野)だから日本だとアンプに頼ることがなくなりますよね。エフェクターに頼って、アンプをクリーンにして、どんだけ自分の音を出すか。
中村)ライブ後の雰囲気も違いますよね。日本は打ち上げも派手にやるし。こっちって打ち上げとかないんですよ。ライブ終わったらサーっとひきますから。日本だと、仕事があっても付き合いで打ち上げに行かないといけなかったり。単発ならいいですけど、ツアーになると大変ですよね。毎晩打ち上げって(笑)
・・・後編に続く
次週のテーマは「ミュージシャンとして。日本人として。」
乞うご期待!


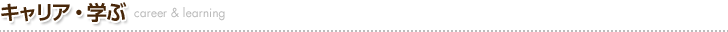
















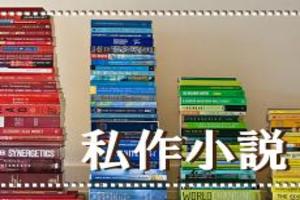

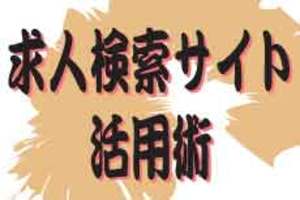
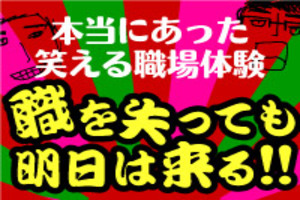

コメント- 名無し (2015-03-30)
- へえーオーストコリアに行ったとは、凄いチャレンジャーだね。私は絶対行かないわ。白人至上主義だし、日本人差別も多い。シーシェパードの国だしね。IQも低いから上から目線で日本人は英語が下手とか言う奴らだし、カレーバッシングも酷い。知能が低いからレイプが多い南北朝鮮とよく似てる。
以前のコメント