踏み絵(前編)
更新日: 2025-10-12
我が息子ケリーは、母親の私が言うのもおかしいが、父親似で目が大きく鼻筋の通った面長なハンサムな若者で、頭も良く、思いやりもあってパーフェクトな息子である。ケリーは、父親を12歳で肺がんで亡くし、それから医者になると一大決心をし、その夢に向かってまっしぐらだった。そのケリーが研修医の期間も終え、シェパトンと言うビクトリア州の田舎町の病院に、今年やっと就職した。私もシェパトンに引っ越すことも考えたが、ずっと働いているレストランのオーナーから頼りにされていて、やめられては困ると言われたので、思いとどまってメルボルンに残ることにした。メルボルンには友達もたくさんいたことも、引っ越しを思いとどまらせた理由の一つだった。離れ離れの生活になってもケリーは2週間に一回は家に帰ってきて、顔を見せてくれた。家に帰れない週は、必ず電話を寄こしていたから、きっと他人から見ると、ケリーはマザコンだと思われただろう。そんな、ケリーがシェパトンに移住して6か月たったある日、「紹介したい人がいるんだ。今度連れて行くからね」と言ったときは、びっくりした。そういう時が来ることを予測していなかったわけではなかったけれど、それはもっと先のことだろうとのんびり構えていた。だから、ケリーが帰る前の晩から、ケリーのガールフレンドってどんな人かしらと、胸がわくわくドキドキし始めた。何しろ子供は息子しかいなかったので、ケリーが結婚すれば、娘もできる。そう思うと、自分が見合いの席に立たされるような興奮で、その晩は寝られなかった。
ケリーの好きな寿司や餃子を用意して、料理の準備も一段落した時、ドアのチャイムが鳴った。すぐに走って行ってドアを開けたい衝動に襲われたが、その気持ちを抑えて、ゆっくりドアの前まで歩いて行って、深呼吸を一つして、ドアを開けた。すると、いつものようににこやかに笑ったケリーが立っていて、「ママ、帰ったよ」と言ってハグしてくれた。そして、後ろを振り向き、「この子がマギーだよ」と、連れてきた女性を紹介してくれた。私はその女性の顔を見て、一瞬ひるんでしまった。見るからに、アボリジニと思われる、色の黒い女性だったからだ。どことなくキャシー・フリーマンに似ているが、ともかく肌の黒さが際立っていた
「初めまして」とにこやかに笑いながら握手するために手を差し出したマギーの手は、手の甲は黒く、手のひらはピンク色だった。一瞬うろたえて、私はどぎまぎしながら握手をした。
「さあ、中に入って」と、ケリーは私のためらいに気が付かないような明るい声で言って、マギーをうちに入れた。
そのあと、用意していた昼ご飯を一緒に食べたのだが、そのとき、どんな会話を交わしたのか、よく覚えていない。マギーが看護師だということと、マギーの家族はクイーンズランドにいるということだけは覚えている。私の頭の中は、「どうして、よりによって、アボリジニの女性なの?白人でも、アジア人でも良かったのに。でも、アボリジニの女性だけは選んでほしくない」と心の中で抗議していた。私の持っているアボリジニのイメージは、酔っぱらって、公園で喚き散らしているイメージ。遠い砂漠のような僻地で、掘っ立て小屋としか思えないような処に住んでいる人たちのイメージ。どうしても、そのイメージが頭にこびりついて離れなかった。
無口になった私に、ケリーもマギーも居心地が悪くなったようだった。だから、食事がすんで1時間もしないうちに、シェパトンに戻ると言い出した。私はあえて、二人を引き留めなかった。二人が去ったあと、私は茫然として、昼ご飯のかたづけもしないで、テーブルの前の椅子に座っていた。人種差別はいけないことだと分かっている。ケリーがアボリジニの友達を作るのは、一向にかまわない。でも、二人が結婚すれば、家族になるのだ。二人の子供が母親似の黒い顔をした赤ん坊だったら、孫として、かわいいと思えるだろうか?そう思うと、自信がなかった。私は二人の結婚には断固反対しなければという思いが、むくむく膨れ上がっていった。
その晩、シェパトンについたとケリーから電話があったとき、私は思わず言ってしまった。
「ママは、あなたがマギーと結婚するのは反対よ」
ムカッとしたらしいケリーの声が聞こえた。
「どうして?彼女は有能な看護師で、明るくてスタッフからも人気がある女性だよ。それなのに、アボリジニだからって拒絶するなんて、ママを見損なったよ。ママはレイシスト(人種差別主義者)だ」
「そういわれれば、そうかもしれない。でも、何が何でも結婚には反対ですからね」
私の言葉に反発したように、プチンとケリーの携帯が切れた。
その翌週から、ケリーから電話がばったりかかってこなくなった。自分から電話をかけるのは癪に障ったので、私は、ケリーが折れてくるまで電話をしないことに決めた。だから気が付いた時には1か月もケリーの声を聴いていなかった。さすがに、寂しくなった私は、ケリーに電話した。電話に出たケリーは不機嫌そうな声で、「今、忙しいから」と、けんもほろろに携帯を切った。そのあと、私は心が暗闇の穴の中に落ち込んでいくように気持ちになった。何とか、二人の溝を埋めなくては。でも、私は絶対、アボリジニの嫁なんて認められない。
ちょさ






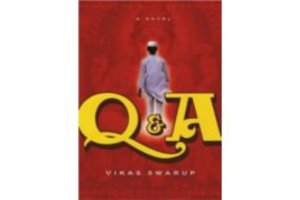






コメント