KIRIN Big in Japan 出演アーティスト インタビュー 後編
アンダーグラウンドシーンを盛り上げるアツい想い
2010年12月14日掲載
KIRIN Big in Japanにご出演された方へのミニ・インタビュー後編をお届けいたします。後編は山懸 良和さん、mamoruさんのインタビューです。お二人の表現方法は全く異なりますが、根底にある思いはユニークでもあり、とても熱いものがあります。
インタビュアー:長谷川 潤、Ryo、河内 雄大
デザイナー 山縣 良和さん

【プロフィール】
山懸 良和 Yoshikazu Yamagake
URL: http://www.writtenafterwards.com/
2005年セントラルセントマーチンズ美術学校卒業。ジョン・ガリアーノの デザインアシスタントを務めた後、帰国。インターナショナルコンペティションITS#three Italy にて3部門受賞。
2007年リトゥンアフターワーズ設立。2008年9月より東京コレクション参加。
2009年オランダアーネムモードビエンナーレにてオープニングファッションショーを行う。(ホームページより抜粋)
--今回のパフォーマンスはどういったパフォーマンスをされるんですか?
シドニーではファッションショーをやったのですが、メルボルンではインスタレーションという形で展示しています。
--具体的にはどういったことをされていますか?
2階で『神様』の展示をしています。あとは1階のあの大きな『ブラジャーとパンツ』を展示しています。
--それぞれの作品のテーマは?
「神様」というテーマは、『世界で初めてファッションショーをしたのが、実は神様だったら』というイメージでストーリーを考えました。さらに『最初のファッションショーが動物の前で行った』という設定の中で、それらのシチュエーションを現代にTranslateしたらどうなるだろうかということを考えました。
現代はH&MやZARAなど、ファストファッションというのがトレンドになっていますよね。約2週間で服を作って店頭で売るスタイルで、それをファストファッションと言います。
クリエーションには結構時間が掛かるものだと思うのですが、このファストファッションに対抗してできないかなと思い、もっと時間を短くして服作りをやれないかなと考えました。一端の布をモデルの前に置いて、2時間くらい前から服を作れないかという発想でやっています。2時間前になったらグルグルグルグル布をモデルに巻いて、最後に残った段ボールの筒の様な杖みたいなものがあるのですが、それを曲げて神様の杖のようして完成という究極のファストファッションみたいなことをやっています。
--ではもう一つの作品『ブラジャーとパンツ』の展示はどういったものですか?
結構前に作ったもので、何体か作ったシリーズのうちの1つなんですよ。『田舎町に怪獣みたいなでかい人が住んでいて、悪ガキがいてその下着泥棒をする』というストーリーを考え、それをファッションショーでやるというイメージでショーを行いました。
--シドニーでの反響はどうでしたか?
反響はすごく良かったですね。Sydney Morning Heraldにも取り上げていただきました。メルボルンではじっくり見てもらおうということで、インスタレーション形で展示しています。ファッションショーはシドニーのみでした。
--いろんな国でショーや展示をされているのですか?
そんなに多くではないですが、学生時代に、ロンドン、パリ、イタリア、オランダなどで行いました。
--こういう形で表現しようと思ったきっかけは何ですか?
ファッションが自分にとってとても大事なものだと感じて、それでなにか表現できないかなと思ったのがきっかけですね。ファッションは誰もが絶対にはずせないものじゃないですか。そういうところで自分の表現が関われることができたらいいなと思ったのがきっかけです。
--オーストラリアでの展示やショーは今回が初めてとのことですが、こちらの印象はどうですか?
僕結構好きですね(笑)。 人がいいですね。みなさんびっくりするぐらい人が良くて。もともとロンドンとパリに住んでいたのですが、こっちの人の方が陽気で差別もない雰囲気が好きです。あとは親日家がすごく多いですね。そこに強い印象を受けました。
サウンドアーティスト mamoruさん

【プロフィール】
mamoru
URL: http://www.afewnotes.com/
2001年にニューヨーク市立大学卒業後、自作の音具や音響機材を用いて、間や、空間性を強く意識した様々な「響き」を即興的に組み上げてゆくサウンドパフォーマン スや、複数の独立した音源を複数のスピーカーを用い空間的に音像を造作するマルチソース・マルチチャンネル型のインスタレーション作品などを国内外のギャ ラリー、美術館、その他の場所で発表。(ホームページより抜粋)
--mamoruさんのパフォーマンスについてご紹介をお願いします。
インスタントヌードルを作るプロセスを音の作品に変えていきます。お客さんは僕がインスタントヌードルを作って食べているのを見ている感じですね。まぁ、見ていると言うか、聴いているというか。
--作っていく過程を音にするっていうことですか?
そうですね。例えばお湯を沸かすときの音をサンプリングして、それを重ねていくとすさまじいノイズになります。お湯の沸く音なんかは普段当り前の音過ぎて全く注目されずに聞き流していますよね。でもね真剣に聴くと意外とすごいと思ってもらえると思います。
パフォーマンスの流れも、ただ僕が淡々とラーメンを作っているだけなので、だからどこか不思議な感じがするわけですよ。見たことあるし、自分でもやっているし、「次はこうなります」というのはまぁ全部予測がつきます。でも作っている過程で出ている音に‘予想外’の印象を受けると思います。
--マイクで音を拾うのですか?
はい、コンタクトマイクロフォンという振動を拾うマイクを使っているので、お客さんが「ワー」とか言っても歓声を拾わなくて、基本的にはコンタクトマイクをつけている物自体の振動を拾います。インスタントラーメンにマイクをクリップして、そこにお湯をかけるのですが、麺は乾燥しているので、お湯をかけるとバキバキバキって割れるんですよね。あの音をキーで録りたいんですよね。
--それはまたなぜですか?
なぜでしょうねー(笑)。 そんなことを普段「すげーっ!」と思うことはあんまり、というより絶対ないわけですよ。それを僕がパフォーマンスとしてやって「すげーっ!」と思うのであれば、自分のキッチンでやっていてもすごいと思うかもしれないじゃないですか。
可能性としてはそういう発見が日常に眠っている、という理論的には成立しますよね。しかもそこにコントラストが生まれたとしたら結果アートがあると思います。普段やっていることなのに、「感動しちゃったー」みたいなことだったら、実際になにが起こったのかというと、普段と何も物理的に変わってないはずですよね。「面白かったな」みたいなことを思ったとしたら、たぶんそこに〝表現″があるのではないかと思うんですよ。
社会的に価値がないと思われているもの使うことで、そのコントラストが出しやすいので、今は日常品とか日常行為を素材として取り上げています。
個人的な興味や価値観だと思うのですが、たとえばダイヤモンドで何か作ってワーって言っても、まぁダイヤモンドすごいからそれはワーでしょうみたいな。金で作ったものは有難いのは当たり前など、そういうひねくれた感じのところが僕にはあるんですよね。なので、社会的に認められてない価値を生み出せたら、それはたぶん作品になるのだと思います。
--インスタントヌードル以外だったら、どういった素材でパフォーマンスをされていますか?
ストローを使います。(ストローを取り出してすこし演奏する)。これは飲むヨーグルトについているもの(上部が伸縮するストロー)ですね。どんなストローでも大体似たような音があって、どんな人でも大体こんな音(ちょっとかすれたようなピーという音)が出せます。でも音の種類としては、とても面白いなーと思います。
世界ストロー財団っていう財団を作って、PR活動を行いながら、「おもしろいなーって思ったら寄付してください」と寄付してもらったもので、ファーストモデルを1000本作ったんですけど、それが大体世界5カ国ぐらいで捌けてしまいました。その間に相当寄付が集まりました。セカンドモデルを2005年に作って、それはもう300本ほど出たのですが、面白いと思う人がいるかぎり続くようなシステムにしようと思っています。
ストローにお金なんて払わないじゃないですか。だけど結構みんな喜んで「買いー」みたいになっていますね。時々酔っ払っている人が買ってくれたりします(笑)。
--それに目を向けたきっかけみたいなものはあるんですか?
どうですかねー。ものすごいこじつけになるかもしれないですけど、自分自身じゃないかと思うときがあります。結局価値がないと思われているものにすら価値が生み出せたら、自分もそのうちの一人だっていうか、まぁ自分で価値がないとは思ってないですけど。
例えば経済的にGlobalizationがめちゃくちゃ進んで、人間自体が消費行為の単なるパーツになっているじゃないですか。マーケティングなど、「一体誰が儲かるの?」みたいなシステムになっていて、そういうのでむなしさを感じているのだと思います。僕自体がむなしさを感じることがよくあるので、日常品を使ったり、飲食の行為をパフォーマンスとしてやっているのも、そういう消費行為を全部転換したい欲望や願望がありますね・・・。消費しているだけだけど作品ができれば、全部ひっくり返せるのではないかなという野望というか野心ですね。
音楽学みたいなところでいうと、基本的に人間が音を出してきた経緯っていうのは身の回りのものからなんですよ。それが特化して楽器になっていく形が自然な形としてあります。僕自身ももともとピアノをやっていましたが、躰に合わないと思ったのもあり、止めざるを得なくなりました。そこで思ったのが、今21世紀に生きていてその辺に物がいっぱいあって、そういう物がそういう可能性をもっているっていうのは当たり前のことじゃないかなと思うですね。大昔も大昔のキッチンから多分いろんな楽器が生まれているだろうし、多分そういうことじゃないかなと思うんです。
ただ押しつけられているじゃないですか。『ストローは吸うもの』のように。ストローはただプラスチックが筒になっているだけじゃないですか。そういう押しつけられた物を積極的に断っていくというハッキング行為ですね(笑)。僕はプログラムのハッキングはできないですけど、ハッカーにすごいsympathyを覚えます。押しつけられたものを、ぶっ壊すのはどうかと思いますが、違う使い方に変えてしまうのはいいのではないかなと思います。
写真:Ryo
ryophotography.wordpress.com
いかがでしたでしょうか? 日本のアンダーグラウンドシーンもますます見逃せませんね! 今後のアーティストの方々の活躍にもぜひご期待ください!


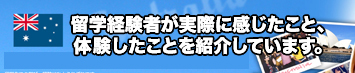
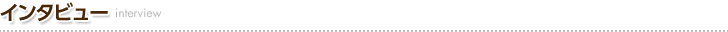
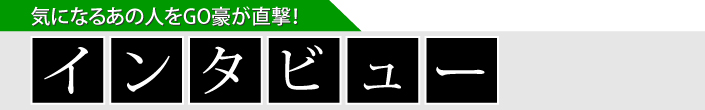






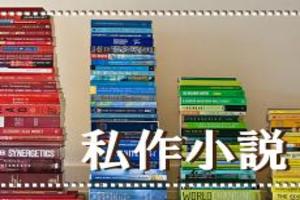







コメント- (,,゜Д゜)∩先生 (2010-12-14)
- こういう人の話が聞けるのは良いですね!もっともっと海外で日本人が活躍してくれるとうれしいです!
- TADAHIRO (2010-12-14)
- カッコイイなあ。。。
以前のコメント