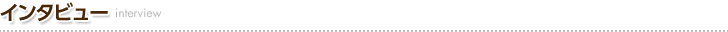映画『俺俺』 三木 聡 映画監督 インタビュー
意味のないものが面白い!ギャグ映画を突っ走る。
[ 13/Jan/2014 ]
日本映画祭にて『俺俺』が上映され、ゲスト出演された三木監督にお話しを伺いました。名だたるテレビ番組の脚本などを手掛け、輝かしい経歴をお持ちですが、意外にも映画を撮影されるようになったのは近年。そのあたりのこともお伺いしました。

神奈川県出身。放送作家・映画監督。
大学時代より放送作家の事務所でのアルバイトをきっかけに放送作家の道へ。『夕やけニャンニャン』、『タモリ倶楽部』、『ダウンタウンのごっつええ感じ』ほか、多数のテレビ番組、ドラマ、バラエティ、映画の他、ヘビナ演術協会やシティボーイズライブ等の脚本・演出を手掛ける。
近年では『時効警察』、『帰ってきた時効警察』の脚本と演出担当。日常から少し外れて行く不条理な世界観、会話や背景などの端々に散りばめたギャグ・小ネタを特徴とし、独特のオフビートな展開は「脱力系」「ゆる系」とも評される。(Wikipedia参照)
『俺俺』は日本で2013年5月に公開。
―『俺俺』の上映会にてお客様の反応はいかがでしたか?
そうですね、ちゃんと映画のツボを理解して笑って下さっているという印象がありました。上映した場所もあると思います。映画に対する見方が洗練された部分をお持ちのお客様が多かったのかなと思いました。上映後のトークで出てくる質問が割と専門的なものあり、細かく見ているなぁという印象でした。
―例えばどんな質問がありましたか?
「アイデンティティの問題をどう考えているのか?」、「日本人はこういう曖昧なアイデンティティの中で生きているのか?」といった質問がありました。
僕にとってはリアルな今の日本人なのですが、こちらの方が見ると「絶対的なものに対して自分がどうあるか」ということがある人たちと、そういうものが日々曖昧な中に暮らしている我々がいて、我々がそのことを提示すると、(オーストラリアの方は)そこに引っ掛かって疑問を持ち、日本人がそういう考え方をするんだなぁと思ったりするのか、と思いました。

©2012 J Storm Inc,
―作品を拝見させていただいたのですが、本当に・・・不思議ですね。
そうですね、普通に笑える喜劇ではないですよね。ひねった感じになっていますので。
元々原作は小説で、「俺」が増えていくことによってアイデンティティの喪失みたいなことがあったので、映画にその原作のスクリプトが当然反映されていると思います。
―これを映画化するきっかけは何でしたか?
それはプロデューサーが「この原作はどう?」と読んでくれと言い始めたのがきっかけです。読んでみたら「これ、映画化するのか!? 大変じゃないですか!」と思いました。実際大変でしたけど(笑)。
インターネット上でFacebookやTwitterをやっていて、実際の自分がやっているけれど、インターネット上である種のキャラクターを演じることもあるじゃないですか? 日常でこういった取材で話している自分と、家族と話しているときの自分が違うとか、営業マンがお客さんに対する時と、会社に戻ってきたときのキャラクターが日常的に違うというようなことは各所にあるのでしょうけど、それがインターネット上だと肥大化していくと言いますか、実際にインターネット上で話をしていた人たちが実際に会ってみると、思っていた人・キャラクターと違う、ということが平気であるわけですよね? そのスイッチしていく感じ見たいなことは「今っぽいなぁ。」と思っていました。
―そう考えると解りますね。映画を観るとなぜキャラクターが増えていくのかな?と。
日本の方はキャラクターが増えて行く事件の解決を意外と求めるのですが、オーストラリアやイタリアなどでも上映したのですが、海外だと「あぁ、そういう話なのだ。」と自分の中で落とし前を付けてもらえますね。
日本の人たちは映画の「なぜ増えたの?」、「これは夢だったに違いない。」といった風になり、―夢だったとかは何も言ってはいないですし、そういう意味ではないのですが―、腑に落ちないと納得しない部分がありますね。
外国ではそういう部分に対して自由なのでしょう。日本のお客様の方が腑に落ちたいと思っているようです。元々日本は農村や農業中心の組織で動いてきた人にとって、腑に落ちないことは社会の邪魔になりますよね? ところが外国はそうではない、というのもあると思います。
―メルボルン、オーストラリアは多民族国家で、隣の人は言葉も目の色、文化も当たり前に違います。だから「納得しあうよりは、知りあうことで良いじゃない?」という雰囲気がありますね。100%相手を理解したり、違う国の人を理解するのはなかなか難しいですよね。「そういうこともある。」というのを知るだけで友達になれる空気がありますね。必ずしも解りあう必要はなく、違うもので当たり前と言う中で、いかに楽しむかというのがありますね。
あまりお客さん同士で制限がかからないわけですね?
―そうですね。日本では一つの答えを最大公約数の方が納得して思いこまないといけないところがありますが、オーストラリアでは子供の頃から自分の意見を持つ教育をされています。
上映後のディスカッションでも質問の数や手を挙げる数が多かったですね。ヨーロッパよりも多かった気がしますね。
日本だともっと遠慮して、誰かが手を挙げると少し言いだすこともありますが、それまでに時間がかかることがありますが、こちらは早いですね。
―冷やし中華を食べているシーンがとても印象的で1人の俳優さんが3人役で、タイミングが合っていて面白かったですね。
基本的にはカウントダウンをして作っています。あのワンカットを撮るのに3テイク撮らないといけません。前の人が箸を割った瞬間を、こちらで音を使わないつもりでカウントダウンをしています。「30、29、28…」と数えながら、28で箸を取ってという感じです。亀梨君は運動神経が良いので、その辺のタイミングを合わせるのが上手です。それが基本の撮影法で、意外とアナログです(笑)。
―そうですね、CGにも見えなかったので、3回撮影して合わせているのかなと思っていました。
しかもレール移動でカメラが動くのでより複雑なのですが、レールのどの位置にカメラがいるかを気にしないといけません。アメリカのようにコンピュータ制御できるようなカメラならぴったりタイミングを合わせられるのですが、僕たちは手動でやらなきゃいけないので…、そのアナログな作業の連続でした。
―そうしますと、1人何役もされているので、撮影はとても大変だったのではないですか?
1カットで8人映っているということは、8テイクを撮影しないといけません。外で撮影する場合は日が動くので影が動きますよね? そうすると影が合わなくなってきます。なるべく天空の高いところに太陽がある時間帯に撮ろうとか、夕方になると影がどんどん動いて光の色も変わるので、後に合成でシームレスに合わせるのが大変になります。天空にあると、30分くらい影が動きがあまり分からない時間帯があるので、なるべく日が天空にあるときに撮影を心掛けていました。
―今回の撮影期間はどれくらいでしたか?
40日間ですね。
―それでも、それくらいの期間で撮影できるのですね。
いや、40日しかなかったですね。撮影には3倍かかるので、日数も3倍欲しいとリクエストしましたがダメでした。
普通に3人のショットですと3人いれば撮れるのですが、それを3回に分けないといけないので3倍かかるわけです。その度にメイクチェンジがあるわけですから。今回は衣装・メイクも大変だったと思いますよ。「今どこを撮影しているのだろう?」とわからなくなっていたかもしれません(笑)。
―映画を撮影しようと思われたきっかけは何ですか?
ずっとテレビや舞台の仕事をしていて、舞台ではコントもやっていました。ふとあるとき、「映画というメディアであまりギャグはやっていないなぁ。」と思ったんです。特に映画マニアでも、映画を勉強してきたわけでもなかったのですが、これだけテレビや舞台でギャグがあるのに、あまり映画でギャグをやらないなと思ったのがきっかけです。
今まで自分たちがやってきたことを―当時はまだフィルムでしたが―映画というメディアに移し換えたときにどういう風になるのか結果を見てみたいと思ったのが最初ですかね。
もちろんギャグ映画はあったのでしょうけど、あまりやっている印象がなかったですね。例えば寅さんですとコメディですし。時々映画で見るギャグが大きく滑っているのを見ると、これだったら別にこういうことじゃなくてもいいのではないかと思っていました。
―小さいころから映画が大好きというわけではなかったのですか?
そうですね。そういう少年ではなかったですね。
―そんな監督が好きな映画は何ですか?
僕はデヴィッド・リンチ監督作品が好きですね。『マルホランド・ドライブ』は名作だと思いますね。コーエン兄弟も好きですし、モンティ・パイソンで言うとテリー・ギリアムさんが好きですね。
―監督が映画を作るときに、こだわりはありますか?
あまり明解なルールは設けないのですが、ちゃんと計画を立ててその通りに進行することで、あまり現場の思いつきで何かやっていくことはしないですね。綿密にセリフのやりとりもリハーサルができるときはちゃんとやって、セリフも脚本にある通りに組み立てて行きます。
そこに役者のクリエイティブが入ってきます。どういう表情をするかとか、どういうリアクションをしたらいいのかというのを含めて役者さんが作っていくのは勿論あります。基本的には設計ラインを最初に作っていこうというのはあります。
今回『俺俺』に関しては、自分でコンテを全て描いて撮るという作業でしたね。絵が下手なので大変ですよ。結構それも大変でしたね。もちろん手作業です。コンテライターを雇ってもらいたかったのですが、「自分で書いた方が早いですよ。」と言われました(笑)。
―今後撮影したいテーマはありますか?
音楽もの、バンドもののバカバカしい映画をやってみたいですね。
―海外で日本映画と言えば昔は時代劇というイメージが強く、最近は全く違いますが、『俺俺』はその中でも新しい映画の流れを感じる作品だと思いました。また海外に住んでいると典型的なことを言われるのが嫌になることもあります。
そういう意味では、まずアニメーションありきでしたね。今回で言いますと『俺俺』は30カ国くらいで上映する機会がありました。
最初に海外で僕の作品を上映したのはイタリアだったと思うのですが、2005、6年の頃上映する機会があって、初めて海外のお客さんの反応を見ていたときに、すでにアニメーションやオタク文化みたいなのが―フランスですと『NARUTO』がデパートで特設コーナーがあってなど―既に広がっています。だから「あなたの映画は漫画やアニメ、コミックの影響を受けているのか?」などとよく聞かれました。
僕らとすれば同じ時代にアニメをやっている人や、漫画を描いている人もいて、僕のようにテレビや舞台でやっている人もいて、そういう共通の中でやっているのですが、向こうとすればアニメなどの文化が影響しているのではないか、と考えるわけですよね。マニアックなギャグですと、2005、6年当時の日本のコントは「日本のもの」という共通認識があり、そういう意味では日本ではその文化の進歩の仕方がとてもすごくて、閉ざされた中でお笑い芸人の数にしてみても、コミック漫画やアニメも毎週大量に作っています。そして日本の中で浄化されていましたね。
アメリカやオーストラリアでもそうですが、そういう共通認識ところからギャグを作らなくてもいい状態なので、なかなか海外では受け入れられないかなぁと思ったのですが、アニメなどがそういう認識を先に植えつけているので、ギャグが受け入れられやすいですね。
―アニメは確固とした地位を築いていますね。
そうですね。そこで見たことがある、感じたことがあることの先にあることや、同じベースにあることに対する受け入れ度は高いのではないかと思います。
1年前にイギリスで上映した際は、日本のコンベンションのようなイベントでしたので本当にコスプレイヤーがびっしりいました。
―それが西洋社会ではカッコいいとかクールという認識がありますね。
そういうアニメの中で見たことのあるようなギャグがあると、理解しやすいみたいです。
僕の映画はどうしてもブロックバスター的な映画館で上映する映画ではないので、例えば今回メルボルンでも小規模の映画館で上映しているので、その時点である程度のベースができていると思います。そういうのが好きな人が集まっているのではないでしょうか? そう意味では楽は楽ですね。
ハリウッド映画のように多数の映画館で上映して、それなりの収益をあげないといけないとなると、客観的に見て僕の映画みたいなのは向いていないなと思いますね。そういう作り方でもないですし。
―監督はテレビや舞台、映画の世界という、全部違うジャンルで活躍していらっしゃるのは凄いですね。
でもやっていることは一緒です。ただし表現の仕方は勿論違います。
舞台は基本的にお客さんがカット割りをしていきます。この役者のこの反応を観たい人はその役者を見ていますし、こっちのツッコミを観たい人はこっちを観ていますし。映画ですとカット割りがありますし、コメディの見せ方そのものを編集でみせるのかなどといった方法論の差もあります。
ただ作ったものの切り口や見せ方が変わっているだけで、やっていることは同じですね。
―別々のジャンルで活動されていてもあまり意識されていらっしゃらないのでしょうか? どのジャンルが好きですか?と、お伺したかったのですが・・・?
どこが一番好きかと言われれば、今はやっぱり映画ですね。映画の現場で構築していくのが好きですかね。テレビや舞台で長くやっていましたので(笑)。
―日本でテレビを観ると、吉本かジャニーズの人が多いですよね?
それは要するに、人材育成を他がしていないということです。昔は映画会社が人材育成をしていたのですが、今は吉本かジャニーズが人材育成をするというシステムになってしまったのには問題があるでしょうね。
僕の『俺俺』もそうですし、今回の日本映画祭でもジャニーズの方が出演されている作品が多く、それに対して批判する映画人がいるのですが、その映画人は人材育成をしていないですよね。日本映画がある時期資本投下をする余力がなかったのでしょう。その中で宮藤官九郎さんや三谷幸喜さんのような未詳劇場の脚本家が映画に出て行ったりしたのだと思います。
売れるものを作るだけが映画産業ではないですよね。どこかで次のトライアルをするための資本投下をしないといけないと思います。そのことを映画業界がやっていなかった時期があったのだと思います。今はそんなことはなくて監督の育成など、機会を広げていると思いますよ。
役者さんはその時期はテレビでも生活していましたね。映画だけでは食べていけないのでテレビやコマーシャルに出て、新しい機材はコマーシャルが入れるといった具合でしたね。映画産業そのものがみんなに介護されている時期があったのだと思います。
―今も日本映画は沢山輩出されていますね。今後日本映画が海外へ進出してくれると良いですね。
小さい作品を含めると年間400本くらい制作されているそうですよ。
一つ問題なのは日本の映画はJポップのように、日本国内という閉ざされた世界で収益をあげられることです。日本のシネコンで上映するとある程度収益が上がり、年間損をせず潤って行ける状況ですと、「日本国内で売れるものを作ろう。」ということになります。彼氏に読ませたい恋愛小説1位が映画化される…ということを考えると、その閉ざされた世界の中で完結してしまいます。
その中で海外向けの典型的な芸者や女子高生が…といった作品が制作されて、全体としては日本の中で収益を完結してしまう中で、今後の世代の人たちがどのように海外に出て行くんだろうなと思います。
―キャスティングに関して、監督はリクエストされるんですか?
します、勿論。そこも楽しみのひとつです。
例えばバンドの編成で言うと、ドラムとベースにあたる人ができたときに、ソロ楽器を取る人はそういう系統ではない人で、急にトリッキーになったときはそう長くは持たないので、ポイントで出る人としてキャスティングを組むのを想像するのは楽しいです。
またキャスティングが決まってから、この役者さんだとこう言った方が面白いだろうなと小修正はしますね。あて書きは基本的にはしないで何も想定しないで書くのですが、演じる人によって言葉が活きてくるようにしますね。
なんとなくバカバカしいという感覚的なセリフも多いので、人に説明すると分からない部分もあります。「何が面白いんですか?」と言われると終わりですからね(笑)。「いや、なんか面白いんじゃないですか。」みたいな。
―あまり理由が無いものが実は面白いこともありますね。
そうですね。意味本能みたいなのがあって、意味や理由が無いものは排除するという傾向がある中で、理由がないから面白いじゃないかということもあるわけです。
役者さんがあるキャラクターを演じて、「この役者さんはこういうことを言わないじゃないか。」と言われると、「言わないから書いているんですよ。そのひとが言いそうなことばかり書いていたら面白くないじゃないですか?」と思います。温厚な人が怒ったのはなぜかというのに興味があるし、この人はこんな酷い言い方をするのかというところに引っ掛かって書くわけですよね。
どうしても一つの意味に集約する傾向がある中で、それを解体したい思いはあります。だからセリフを憶えにくいとよく言われます(笑)。意味が解体されているので、なぜこの言葉が出て来るのかわからなくなって、「三木さんのはセリフが憶え辛いです。」と言われます(笑)。
―最近は『ガッチャマン』といった子供時代に観ていたアニメのリメイクや実写化が多いですが、そういう傾向はどう思われますか? 個人的には原作を越えられないのではないかと思います。
そうですね。それでも保守層といったところに受け入れられるのではないかと思います。
例えばジャニーズといった人気のある役者と、オリジナルに出演していた人が共演するとなると、多くの出資者やスポンサーにお金を出してもらおうとしたときに、多くの年齢層に受け入れられやすいです、と言いやすく、また企画として通りやすくて、さらに出資をジャッジする人が子供の頃に観ていた作品だと理解してもらいやすいですよね。
実写化作品が成功し始めるとそれだけになっていくので、「それだけではないですよね?」という疑問はあります。
―最後に今後『俺俺』をご覧になる方へメッセージをお願いします。
今の日本で生きている日本人に対するブラックコメディなので、その部分を楽しんでください。特に海外にいる日本人の方がどのように観て感じるのかというのに興味があります。真面目に筋を追っていくとわからなくなる特殊な映画ですが(笑)、ご覧になって感じたことを発信していただけたらと思います。
俺俺 オフィシャルサイト
ore-ore.jp
● ● ● ● ● ● ● ●
>>編集後記
つい先日まで日本でテレビ放映されていたドラマ『変身インタビュアーの憂鬱』も三木監督ワールドが弾けていた作品でした。強行スケジュールで来られたそうですが、また来たいともおっしゃっていました。「そのためには映画作んなきゃな。」と。次の作品も楽しみです。
三木監督、ぜひお待ちしています。有り難うございました。