『野火』 Fires on the Plain 塚本晋也映画監督 インタビュー
戦争の残虐さ・理不尽さを映像化
2015年12月4日掲載
第19回 Japanese Film Festival で、目玉作品として 塚本晋也監督の『野火』 Fires on the Plainが上映されました。
原作は大岡昇平の同名小説。 戦争体験を持つ作者が描いた、戦争の残虐さ・理不尽さを、それを見つめる主人公の心理描写を、塚本監督は見事に映像化しました。
塚本監督は、『野火』 Fires on the Plainの上映に映画祭ゲストとして来場。 Australian Film Critics AssociationのPeter Krausz 氏と対談し、また、観客とも質疑応答を行ないました。
『野火』 Fires on the Plainの上映直前、塚本監督にお話しを伺いました。

―オーストラリアでのお客様の反応は、もうご覧になりましたか?
まだです。まさに今日これからです。
実はオーストラリアは、今回が始めてです。 映画は随分前に「鉄男」とか最初の頃から上映していただいているのですが、自分は来ていないので。 是非来てみたいと思っていたんです。
―『野火』を制作された切っ掛けは何だったんでしょうか?
原作を高校生の時に読んでから、頭に刻み込まれて離れませんでした。
作ろうと考え始めたのが何時だったか覚えていないんですが、30代となった頃には、はっきりと作ろうと決心して、具体的に動いていたんですが。 大きな規模なので、お金が集らなくて先延ばしにしていました。
40代の半ばでも、まだ制作費が集まらなくて。 それが3年ぐらい前、まだ、お金は集ってなかったんですが、世の中の動きとかから、今を逃せば作れなくなると感じて、むりやりに作り始めました。

―監督・俳優・脚本・撮影・美術・編集など、一人で行われている理由をお聞かせください。
自主映画では、それが一番やりやすいやり方ですので、それが自分のスタイルになっています。
ただ『野火』に関しては、そのスタイルでするつもりはなかったんです。 原作があって、普遍的な話ですので、いつかはお金が出ると思っていたんですね。
まあ大きな金額なので、大きな監督になって信頼されれば出ると思っていたんですが、それが出なくて。 それで先程言ったような時期が来たので、いつものスタイルでむりやりにやったという感じですね。
この映画だけは、本当は分業体制で作りたかったんです。
―撮影期間から制作まではどれくらいだったんでしょうか?
撮影期間は、人を集めてから半年です。 準備しては撮影、準備しては撮影でしたから、実質の撮影期間はもっと短いです。
長い間、計画していたんですが、やり始めてからは、かなりのスピードでした。

―公開されて日本での反応はいかがだったんでしょうか?
正直どうなるかな、と思っていたんですけど。 みなさんが、今の時代の動きに敏感になっていき、もの凄く沢山の人達が興味を持って見に来ていただきました。
それこそ、老若男女ですね。 『野火』というタイトルに魅かれて来ましたという年配の男性、子供を持つお母さん、若い人達まで幅広い年齢見に来ていただいて、何かを感じていただきました。
みなさん、すぐに言葉にならないようでしたけど。 確かに何かを感じていただけたようでした。
―『野火』という作品に込めた一番の思いというのは何でしょうか?
戦争体験者の方にも、インタビューしてお話を伺いました。 戦争というのはこういうもんなんだよ、ということです。
人によっては「さすがにあそこまではないでしょう。ホラーとして作っているんでしょう。」と言う人もいるんですけど、「実際にあったことで、戦争すると、こういうことが起こるんだ」ということを皆さんに知ってもらいたい。
問題提起でもあります。 事実として受け取ってもらって、その上で皆さんがどう判断するか、ということですね。
 © Shinya Tsukamoto / Kaiju Theater
© Shinya Tsukamoto / Kaiju Theater
―1959年の市川崑監督の『野火』を意識はされていたのでしょうか?
市川崑監督は尊敬する素晴しい監督です。 1959年の映画も大好きなんですが、『野火』に関しては、アプローチが全然違うので、あの素晴しい映画が先にあるからといって、撮るのをやめようという気にはなりませんでした。
例えば、市川監督の映画は、すべて日本で撮っています。 当時はフィリピンに行けなかったのかも知れません。 その分、人間を深く描いているんですけど。 自分は、ちっぽけな人間と大自然のコントラストも描きたかったことの一つですので、現地フィリピンに拘りました。
―撮影が終っての達成感はいかがでしたでしょうか?
実感がどうもなかった。ヘンテコなものができたな、という感じでしたね。 これで良かったのかどうかも分からなかった。 長い間作りたかったものが出来たのに。
日本で上映して、お客さまの反応を見て、「ああ終ったんだな」と感じました。
―最近、日本映画が世界のあちこちで出品され、公開されています。 海外からの日本映画の評価を、監督はどのように感じられているんでしょうか?
23年前でしたか、インデペンデントの「鉄男Ⅱ」という映画を持って回ったんですが(参考:塚本作品 国際映画祭出品データ)、 そんなことをしている人は誰もいませんでした。
それまでの日本映画では、黒澤明監督、小津安二郎監督、溝口健二監督、次の世代で、今村昌平監督、大島渚監督くらいで、その後はずいぶんと間が開いていたんです。
日本映画でも、インデペンデントでも、とにかくユニークなものを何か持っていたら、大いに歓迎される、ということが分りました。
自分が一番お世話になっているベネチア国際映画祭とか、最初に「鉄男」を持っていったローマ・ファンタステック国際映画祭とか、特にイタリアというのは、本当にヘンテコな物を受け入れてくれる国だな、と感じています。

―監督にとって、映画作りというのは何なんでしょうか?
凄く難しい問題ですね。今、4つも5つも答えが出てきてるんですけど。
1つにはただ実験的というだけでなく娯楽でありたいということ。 もう1つには何かその時代とつながるものでありたいということ。 その合体ですね。
その合体がうまくいった時には、非常な達成感を感じます。
―俳優をやられる時は、監督をする時とは全然違うものでしょうか?
全然違いますね。
他の監督の映画に呼んでいただく時は、 主には好きな監督の映画しか参加できないです。
知っている監督さんじゃない場合は、プロの俳優でないので本当にご迷惑をおかけしないでできるかを慎重に考えます。

―これから野火を見るオーストラリアの人にメッセージをお願いします。
この『野火』は、第二次世界大戦のフィリピンのことを描いてはいるんですけど、映画の中では特に明かにされていません。
みなさんの自分の国に置き換えて、戦争というものはこういうものなんだよ、ということで考えていただきたいです。
―次回作やこれからの撮ってみたい映画の構想とかは、いかがでしょうか?
一杯あるんですけど、今は長い間の宿願だった『野火』を一人でも多くの人に届けることに活動していきたいです。
これをきっちり終らせてから、次のことに取り掛かりたいです。
―人生のこの一本の映画を選ぶとすれば?
黒澤明監督の「七人の侍」です。
自分とはスタイルから何から、全然違うんですけど。
活劇性があって、実験的手法も使われる黒沢監督が大好きで、 これには映画が全部が入っている。
大多数の人が同じように考えていると思いますけど、「七人の侍」です。

インタビュー:長谷川潤
文・写真:矢部勝義



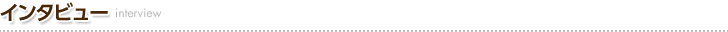
















コメント