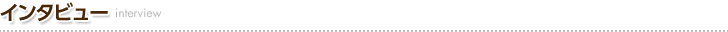『図書館戦争』 佐藤 信介 映画監督 インタビュー
日本映画祭ゲストとして来豪
[ 7/Dec/2013 ]
11月28日からメルボルンで開催されている日本映画祭。その中の一作品『図書館戦争』の上映に合わせ、ゲスト出演された佐藤監督にお会いする機会を得ました。熱意のこもったお話や映画に対する様々な思いを聞くことができましたので、ぜひご覧ください。

広島県出身。映画、アニメーション監督、脚本家、ゲーム製作者。武蔵野大学卒。
大学時代に監督した『寮内厳粛』がぴあフィルムフェスティバルにてグランプリ受賞。市川準監督の『東京夜曲』(97)、『たどんとちくわ(「たどん」を担当)』(98)、『ざわざわ下北沢』(00)、および行定勲監督の『ひまわり』(00)、『ロックンロールミシン』(02)などの脚本を執筆。このほかドラマの演出や脚本も手がける。
2001年に尾崎豊の代表曲に初めて使用許可が下りた『LOVE SONG』で監督メジャー・デビュー。近年では織田裕二主演『県庁の星』(06)の脚本担当、2007年公開の『砂時計』を監督。『ホッタラケの島/遥と魔法の鏡』では監督と脚本として参加し、国内外の映画祭にて賞を獲得。2010年には『GANTZ』の続編『GANTZ PREFECT ANSWER』を監督。
『図書館戦争』は日本では2013年ゴールデン・ウィークに公開された。
―オーストラリアは初めて来られましたか? メルボルンの印象はいかがですか?
はい、初めてです。
メルボルンは全くイメージなく来たのですが、古い街と新しい街が混在していておもしろいなと思っています。歩けば歩くほどいろいろ面白い街角があるなと思って、いろいろ写真を撮っています。
―『図書館戦争』についてお伺いしたいのですが、今回は原作が小説でその実写化にあたり、監督のこだわりや、注意した点はありましたか?
原作を映画化するのは日本ではとても多く、僕も何度かやっています。
今回に限ってだけでなくいつも思うのは、原作の世界観に一番共感、惹かれた部分は何としてでも拡大して映画の中に込めたいという思いと、小説の中で見えてこない部分―もちろん小説は文字ですから、当然全ては頭の中で見えているだけで、現実には見えていない―そういった見えていない部分を、映像の中で拡大して映し出していくというのをやらないといけないなと注意して心掛けています。
ある部分では原作に忠実に描くという思いもあるのですが、またある部分では映画の一番得意な部分、映画で一番面白くなる部分を拡大解釈しながら、縮小再生産にならないようにすることをいつも念頭に置いています。
『図書館戦争』を映画化することを考えていたときに、その勝算と言いますか、「これだったらできるのではないか、良い映画になるんじゃないか。」という思いがどこかで見つからないと、漠然とは映画化はできないものです。
特にこの『図書館戦争』という映画はどういうタイプの映画かと言われれば、ふっと思いつく映画がなかなか無いタイプの映画だった気がします。すごくスタイリッシュなアクション映画だとか、すごくコミカルなギャグ映画だとか、そういうことではなかったと思います。パッと「あんな映画!」と言えないタイプの映画だと容易に思えますね。
最初に自分なりに考えたのは、これを映画化するに際し、どういうふうにすれば映画として面白くなるかということでした。原作ファンが観て喜ぶことももちろん大事ですが、映画として原作を読んでいない人、全く何も知らない人でも面白がってもらえる映画、ということを見つけるのが一番砕心したところです。
―私たちのような海外に住んでいるものとしては原作を読むチャンスも少なく、情報があまりなく拝見しました。最初はコメディタッチなのかと思ったのですが、アクションもあり喜怒哀楽もあり最初の印象と変わりました。そこが面白かったです。
そこが面白いところでもあり、難しいところでもあります。
「政府がある検閲を実行し、思想的に弾圧支配している近未来SF」と言うと、だいたいダークなイメージで、暗いタッチでみんな虐げられていて・・・というようなイメージなりますよね。最初のきっかけはそんな雰囲気に感じるのですが、話が進むとものすごく明るいタッチで、そこが他にはあまりないことだなと感じます。そこが面白いところなのだろな、という気がして、撮影する時も明るいトーンをとても大切にして作るようにしていました。

©Library Wars Movie Project
―戦闘シーンも多いのですが、全体的に明るく、楽しんで観ることができますね。
冒頭が暗いタッチで始まるのですが、過去がどういう風になって今に至ったのかを映像で描きたかったんです。いくつかの文章で「現代はこう時代である」というのを文字で謳うパターンもあると思うのですが、今回に関しては「日本がこういう風な道をたどりパラレルワールドに入って行った」というのを映像でやりたいと最初から話していました。その辺は原作にない映像ならではの描き方だと思います。最初は暗く始まりますが、どこかで転調して明るいイメージになるというのをタイトルまでに描きました。
―タイトルが出るまでに時間がかかりましたね。
今回はその方が良いのではないかと思いました。
映画が始まって10分経つか経たないかの頃には、主人公「郁」が希望に溢れて図書隊―10分前には知りもしなかった軍隊―に入って、明るい日常を過ごしているところにグッと入っていけるような構成を目指していました。
―主演のお二人がとても魅力的で、雑誌『ダ・ウィンチ』の投票で選ばれたそうですね。
イメージ投票の結果があのお二人(岡田准一さん、榮倉奈々さん)で、イメージのキャスティングでイチオシでした。原作にもこと細かくイメージ描かれているので照らし合わせると「まぁこの二人だよな。」というのはありました。
その他プロデューサーとの話し合いなどもありましたが、皆さん快諾されたそうです。
―作品はとても面白かったので続編はないのかなと思いましたが、いかがですか?
そうですね、もちろんそういう声をたくさんいただいていて、続編に対してはみんな前向きに考えています。
やってみて、みなさん自然に役に入り込んでいかれたようです。特に眉間にしわを寄せて役について「こうすべき、ああすべき」と話したわけでは無かったですね。
『図書館戦争』はテレビアニメシリーズもあり人気があったのですが、あまりアニメに描かれたキャラクターを追求しすぎると物マネみたいになってしまうのは嫌だなぁと思っていました。
役者さんがいて、その役者さんのポテンシャルというのは、良い部分も悪い部分もあるので、そういうのが透けて見えてくるといいなといつも思っています。ですので、あまり型にはめ過ぎない方がいいなと思っていて、自然に出てくるところが画面に映るといいなと期待しながらいつも撮影しています。
―役者さんがナチュラルな感じはありましたね。
面白いところもあれば、偶然出てきたようなナチュラルなところも出てきたりして、この映画は比較的よく撮れたなと思っています。
―今回オーストラリアで上映されたところはご覧になられましたか? お客様の反応はいかがでしたか?
みなさん受けていましたね。笑っていたし、拍手もありました。
先入観なしに見ていただけますよね。もちろん中にはアニメのファンの人もいらっしゃると思いますが、何も知らずにご覧になられた方もいると思います。
そういう人の反応を見ていると、役者さんに対する先入観、ストーリーに対する先入観もないですし、あるいは日本でこの映画を見ているときにあるような、日本で作られたSF映画ですとか、恋愛映画ではなくSF映画を観る感覚…、というのも無いですし、割とストーリーに入ってご覧になられていましたね。楽しんでいらっしゃるので、気持ちが良いと言えば良いです。
メルボルン以外にモントリオール、サンフランシスコで上映があった時にも観客の反応を見ているのですが、みなさんが笑っているところは受けています。そうするとだんだんみんなの反応の平均値が解ってきているのかもしれません(笑)。
―やはり国によって違いますか?
やっぱり違います。いや、大筋同じですね。ここは必ず受けるなぁというのはありますね。今回はコミカルな部分もあったので、より分かりやすいというのはあったと思います。
でも総合的にすぐに話に入っている感じはありますね。近未来物でパラレルワールドものなので、話の前提がすごく重く、その梯子を踏み外すと「なんだっけ?」ということになるので、そこは僕が作る前に気を付けた部分です。
特にこの映画自体は日本のマーケット向けに作っているのもあるので、日本ではパラレルワールドものや『ハンガー・ゲーム』的映画はあまり実写映画では無いです。なので「え、ほんと?日本映画で?」とちょっと斜に見られているところがある気がします。だからなお、「日本がこういう時代変遷を経て全然違う現代になりました」という冒頭部分は丁寧にやりたいなと思っていて、観客が踏み外さないように自然に入っていけるようにいろいろ気を使っていましたが、他の国の方々が見られていても、スッと入って来られているのを見て、とても手ごたえを感じましたね。
―監督自身のことをお伺いしたいのですが、映画監督になるきっかけは何でしたか?
元々物心がついたころには映画を見ていました。父親が映画好きで、記憶にない頃から一緒によく見ていたらしいです。記憶が付いたころにはもう映画が好きで、映画をずっと見ていました。
それから絵に興味が出てきたり、小説に興味が出てきたりして、絵描きか小説家になりたいと小学生の頃は漠然と考えていました。絵と文章では少し方向が違うので中学生の頃にはどっちになろうかと本気で悩んでいましたね。
高校一年生になり、大学の進路を決めて行かなければならないときに、絵と文章では大学が全然違うので本格的に真面目に悩みはじめました(笑)。今でも憶えているのですが、その頃ふと「あれ?」と気付いたことがあって、「要は二つ一緒にやろうとしたときに、俺が一番好きな映画を俺が作ればいいんじゃないか。」と気付いたんです。その瞬間から「俺は監督になろう。」と思うようになりました。
映画は好きでしたが、まさか「自分で作る」という発想はなく、映画はどうやって作っているかもわかりませんでした。文章でしたら書けばいいですし、絵も自分で書けばいいですし。「映画って、そうか、誰かが作っているんだよな。」、「あ、そうか俺が作ればいいのか。」と思ったんです。
地元は広島県の田舎で、映画館もなく、当時レンタルビデオもなく、またテレビも4チャンネルしか入らず、そのうち二つは国営放送ですから(笑)。映画とかテレビはほとんど放映されないわけです。もう映画館に行くしかないんです。テレビでは洋画劇場などもやっていましたが、21時以降はテレビ禁止だったので、当時映画はすごく観たいのに観られないという渇望がありました。
映画というのが自分にとってとても欲しているものでした。なので、よく自分で未知の映画を頭の中で想像していましたね。自分なりに「こんなのがいいなぁ。」とかそういった想像をしていました。
―それが監督になられてから実際の映画へ使用されたことはありますか?
そういう気持ちで空想したことは無かったですけど、やはり今作っている映画の延長線上のようなことは思っていたと思います。観た映画のさらにこんな感じのという観たことのないような映画を空想していましたし、自分自身でもそういう行為が好きだという認識もありました。
だけどそういうことをやりながらも、「自分で作る」という発想はなぜかなかったですね。高校1年生の時に「自分で作ればいいんだ!」と気付いてからは、「俺は映画監督になる。」とみんなに言っていました(笑)。「バカか。アホか。」とみんなに言われながら頭に来ていたのですが、どこかでできる気がしていました。
それでなぜか「映画をやるには絵を勉強しなきゃ。」という方向になりました。
―それは、なかなかそういう風には思わないですよね。
そうですね、でも僕自身にとっては自然なことでした。それで美術の予備校に通って美大に進むのですが、後で予備校の先生にそういう話をしたところ、「佐藤は映画を『絵』だと思っているからだよ。」と言われ、「あぁ、そうかもな。」といまだにそういう気がしています。
それから絵を勉強し始めて、そこから自主映画を作成するようになって今に至るという感じです。
―監督が青春時代に影響された映画や好きな映画は何でしたか?
大学生の頃にはビデオもあったので、それこそ一通りヨーロッパの映画や日本の古典映画、アメリカの古典映画などもう沢山観ました。
80年代は田舎にいて、当時田舎の映画館にはハリウッド・ブロックバスターしか入って来なかったですね。いわゆるスピルバーグ監督の時代です。あの頃もいろんな監督の映画がありましたが、いまだに生き残ってやっているのはスピルバーグ監督くらいですよね。今観ても一つずつのシーンがよく考えられて撮られているなと思います。やはりスピルバーグ監督作品をよく見ているので、好きだと公言しています。
―そうですね、当時は映画を観ると言えばスピルバーグ監督の映画を観ることと言っても過言ではなかったですね。
そうですね。よく昔から映画全体を観るだけではなく、あのシーンをもう一度観たいなと思って、シーンをつまみ見したりしますが、スピルバーグ監督作品はよくできているなと思うシーンが沢山あります。いまだに現役でやっていらっしゃるし、凄いと思いますね。
日本では成瀬巳喜男監督の映画がとても好きで、よくカット割りなどを分析したりしています。大学では映画の授業がほとんどなかったので、自主映画を作るときにカット割りはどうやってできているのかなぁとひも解いて、研究はしていましたね。
―映画を作る際に大事にしていることや気を付けていることは何ですか?
まだ達成していないことは沢山ありますが、全体を観たときに「あ、いいな。」と言いますか、映画の世界に入って、終わることが寂しく感じるものが作りたいなと思います。
よく思い出すのが、昔映画館で映画を観てから家に帰るのがさみしいなと思っていたことです。祭りの後のような。そういうのがたまらなかったので、そういう映画がいいなと思います。
逆に顕微鏡のように細部に焦点を合わせると、非常によくできているな、緻密で考えられているなと思える映画を目指したいと思い、なるべくそうなるように頑張っていますし、いつも目標にしています。
―これから取り組んでみたい題材やテーマはありますか?
今やっていることを追求したいのが一番あります。今の時点では、例えば『図書館戦争』で描いたような、ある種の問題とそれを裏返すような希望が映画の中で見えてくるようなものには、映画ならではのカタルシスというのがあると思います。
特にテーマを強く推すのではないのですが、現代社会でふとそういう映画に触れて、気持ち良く劇場を出て、言葉では表せないようなテーマを感じてもらって、何かの加点になれば良いなと漠然とそういうことを思いながら作っています。
今はそういう映画を率先的に作っていきたいです。どういうテーマのどういうジャンルの映画を作っても、最終的には観終わった時に「ずいぶん遠くに来たな。」と思える映画を作りたいと思っています。
―とても良い表現ですね。感覚的にわかる気がします。
自分がもっと年をとれば変わるかもしれませんが、今は割とそういう映画が自分の理想として到達したいと思いながら作りたいと思っています。
もうひとつは映画そのものの不思議と言いますか…、映画とは何かとかいろいろ思うのですが…。
―そうですね、それも質問の一つでして(笑)、監督にとっての映画とは何ですか?とお伺いしようと思っていました。
そうですね・・・、黒沢明監督がアカデミー賞の特別名誉賞を受賞する際に、「映画とはまだ何かわからない。」と言ってみんな笑ったそうで、その気持ちが解ると言えば横柄かもしれませんが。本当に「映画とは何か? なぜ映画があるのか?」とよく思います。
片や1960年代にゴダールが「映画とテレビの違いは何ですか。」と聞かれたときに、「映像と音、どちらも同じだ。」という発言をしていて、今でも「あぁ、そうだな。」という思いと「じゃあそれで、映画とは何なのか?」と思ってしまいます。
映画を撮影していると、「映画っぽいね。」、「ドラマっぽいね。」という話がよく出て、ドラマを撮影する監督が「今度は映画っぽくやりたい。」とおっしゃるのですが、じゃあ「映画っぽい、とは何なのか?」と思います。また何かの映画を観たときに、「やっぱりドラマの監督だからドラマっぽかったよね。」という話が出てきたりして、でも「ドラマっぽいって何か?」とそういったことを日常的に考えています。
映像が連鎖して作られる映画の映画っぽさというのは何かと思いますし、そこから発展して「良い映画とは何か?」と思ってくるんですね。自分なりに答えが見つかったと思った瞬間に、それは違うなと考えながら映画を作っています。
でも答えが見つかってしまう面白くなさ、もありますね。それを映画批評として追求している方もいますが、僕の場合は自主映画からやっていて、映画を作りながらそれを見つけようとして足掻いているのかもしれません。そういうある種の幻想を追っていると言うか、どこかに答えがあるのではないかと思いますね。
自分で小さな映画を作っていても、今回の『図書館戦争』のような映画を作っていても、思っていることは同じで、どこかに幻想の自分なりの良い映画があって―みんなが言う良い映画ではなく―それに向かっていきたい衝動があります。それを常に思っていて、またそれが逆に楽しくてやっていますね。
僕にとっての映画は何かと問われれば、「それは現在追求中なのでちょっと待ってください。」という感じです。いつもこうじゃないかと言い表したいと思いながら、明確に言葉ではなかなか言い表せないですね。
―私たち観る方からしますと、2時間内に非日常空間があって喜怒哀楽があります。山田洋二監督がおっしゃっていた言葉が印象的で、「普通の人間には普段の生活にいろいろストレスや悩みがある中で、映画を観終わった後に雨がサーっとあがった晴れ空になるような感じ」というのは本当にそうだなと思います。映画を観た後はさわやかで元気が出て、感動したら自分に置き換えて「頑張ろう!」という活力源があると思いますね。別世界へ連れて行ってくれますし。昔は映画館に行くことがお祭りごとのようで、今でこそDVDなどがあるので簡単になってしまいましたが。今回『図書館戦争』を観させていただいて、そういう気分になったので今日お会いできるのを楽しみにしていました。
有り難うございます。
僕が考えることではないかもしれませんが、映画の未来を考えますと、例えば映画を1年間見なくても生きてはいけますし、映画が無ければ死んでしまう人もいないでしょうし、「映画は要るのか?」と言われれば「要らないかもしれないな。」とたまに思うわけです。
でも映画には気持ち良くなれて、他にそういうものがあるのかと言えば、他では味わえない良さがあって、それはそれで素晴らしいと思います。
例えば音楽は、レストランだったら「ちょっと音楽でも流していないと。」ということで必要不可欠なものだと思うのですが、映画は「そこまで必要なものではないのかな?」と思うことがあります。ただ現代を見まわすと映像は今後も拡大して、もっともっと必要とされるでしょうし、そうであればあるほど―基盤体なところやバラエティ的なところも必要ですが―映像でひとつのドラマ紬を人々に与えていくのは決して無くならないと思います。それがどんな形で見られようと。
そうすると自分たちがやっていることも正当化されて、必要なものと考えていいのではないかと思います。日本や世界の映画界のことを考えるとこのままで大丈夫なのかと思うこともありますが、映像でフィクションを見せる、映像によって本当のこと・ものに思わせる、笑わせる、泣かせるという映像によって感情に訴える表現は、決して世の中がどう変わっても、もしかしたら無くならないかもしれないと思うと、自分自身もちょっと希望を持てる気がします。
―やっぱり映画は「娯楽の王様」だと思いますよね。
そうですね。「娯楽の王様」と言うと「そうだ!」と思いますが、「映画の黄金期」と言ってしまうと何か過去のもののような気がしますね。昔ながらの映画館で映画を観るスタイルが、ある意味飽和状態になっていることなのかなぁと思わなくもないですね。
飛行機に乗ってトイレから戻ろうとすると、全員が映画を観ているときがありますよね(笑)。
―3本くらい観るときもありますしね。
「どれだけ好きなんだ。」と思うのですが(笑)、時間が有ってじっとしていて、そこにモニターがあれば、いろいろ観るけれど映画を観始めるというのは、ある種自然な行為なのかなとも思います。音楽も必要ですが、映画も人間の根源的な基に根ざしているのかなと思うこともあります。
先ほどの「映画とは何か?」ではないですが、「何か」は飽くなきテーマとして追求し続けられると思うのですが、「映画は必要なのかな?」と思うときはそういう意味でも未来はあるのではないかと思います。形はわかりませんが、永久に残っていくのではないかと思っています。
―忙しい中でわざわざお金を払って映画館に行って映画を観るというのは、すごいですよね。
今回の『図書館戦争』は日本ではすでにDVDも出ているので、久しぶりに大画面で観たのですが、大画面で観る良さはかけがえのないものだなと思いました。大画面じゃなきゃいけないというわけでもなく、小さい画面で観る良さもあると思いますが。今は封切後数カ月で観られなくなり、もう一度観る機会が無いのですが、たまには終わった映画でも大画面でみる機会があっても良いのではないかと思いましたね。
僕たちも映画を作るときには、大画面用に様々な調整をしています。それが最大限に表現できるのが大画面で良い音響で観たときなのですが、なかなか理想的に観られるところが無いと言うと勿体ない気もします。
特に『図書館戦争』は小さい繊細なところから、映画ならではの迫力まであって、割と幅が広いと思います。ラブコメタッチから戦いの極限まで振り切るので、劇場で観てもらえると嬉しいですね。
―『図書館戦争』は12月8日(日)に再上映されるのですが、ご覧になられる方へメッセージをお願いします。
今後DVDでご覧になられる方もいらっしゃると思いますが、今回大画面で放映されるのを観て、理想的な環境でこの映画を観ていただけると思いました。もうこの映画のそういう機会もなかなか無いと思います。
今回日本映画祭ということで他にも楽しい映画もあると思いますが、『図書館戦争』は絶対にこの映画の2時間以外ではみられないような世界、現代の日本を描いたものではなく異質な日本を描いているのも面白いと思います。とてもキュートなラブコメディから、本当にまっしぐらなアクションや戦いありの総合エンターテイメントとして楽しんで観ていただけると思いますので、この機会に観ていただけたらと思います。観て損はないと思います。
―もう一度観たいくらいです。あの2時間はあっと言う間でしたね。
いろいろな楽しみ方ができると思います。僕たちが思っていたのはカップルで観に行ったときに、女性も楽しめるけど、男性も楽しめるものを目指していました。僕も男性の一SFファンとして楽しめる映画にしたいと思って作っていましたし、主人公が女性で、手のちょっとしぐさでキュンとできるような小さな世界を描けるといいなと思っていました。
上映会でもみなさん楽しんでいただいていたので、とにかくこの機会に観ていただけたらと思います。
―僕もあんな可愛らしい子にドロップキックをされたいですね(笑)。
そうですね(笑)、そういう楽しみ方もありますね。
佐藤信介監督の映像制作レーベル Angle Pictures
www.anglepic.com
図書館戦争
toshokan-sensou-movie.com
第17回 日本映画祭
japanesefilmfestival.net
>>編集後記
穏やかな中に熱い想いを沢山聞かせていただき、本当に楽しくて素敵な時間を過ごさせていただきました。もっともっと聞きたいくらいです。
次作は松岡圭祐さんの人気ミステリー『万能鑑定士Qの事件簿』を綾瀬はるかさん、松坂桃李さん共演で、来年半ばに公開される予定です。今回のメルボルンへはその撮影終了直後に来られたそうです。日本へ戻ったらすぐに編集作業に入られます。
またファンから『図書館戦争』の続編制作の声も多いそうで、監督の頭の中には既に構想もあり、役者さんやスタッフも続編に意欲的だそうですので、近い未来に期待したいです。
貴重なお時間をいただき、本当にありがとうございました。
Interviewer: Jun Hasegawa
Photo & Edit: Yoshimi Okita