ウルルの石 第二話 田中幸雄の話(完結)
更新日: 2009-11-15
それからは、母と僕の末期癌との戦いが始まったのです。母の好物の果物や魚を買ってきて、食べさせようとしても、母の体が受け付けなくなっていました。すぐに、吐き出すのです。流動食にすると、一さじか二さじ食べますが、それだけでは栄養失調になってしまいます。結局栄養剤を点滴してもらいました。痩せているとはいえ、母をトイレに連れて行ったり、風呂に入れたりするのは、かなりの重労働でした。そんな時、母の妹の和恵おばさんが二日に一回は訪ねてくれて、とても助かりました。特に母の体力が衰えてトイレにも行けなくなった時、僕も母の下の始末をするのに抵抗がありましたが、それ以上に母は男の僕が始末をするのに抵抗があったようです。そんな時、和恵おばさんが訪ねてくると、母は和恵おばさんには遠慮なく下の世話でも頼めると言って、ほっとしたようでした。僕は近所に食べ物や雑貨を買いに行く以外、外出するのもままならなくなりました。それも出かけている間に母に異変があったら大変だという思いから、焦って必要な物だけ買って慌ててうちに帰りました。最初の2ヶ月は、母と将来のことについて話すゆとりもありました。ところが2ヶ月目を過ぎた頃から、母の胃の痛みが耐え難いものとなり、往診にきてくださったお医者さんの鎮痛剤も効かなくなってしまいました。そんな時母は痛みで顔を歪め、のたうち回るのですが、それをどうしようもなくただ見ているだけの僕は、自分の無力さに泣きました。そのとき、安楽死反対と言う人は、母のようにもう助かる望みのない患者の苦しみを目の当たりにしたことがない人だと思いました。そして、何度も思いました。この母の苦しみを少しでも軽くしてあげられたら、短くしてあげたらと。だから、母が亡くなったときは、思わず「よかったね、お母さん。これで、もう苦しまなくてもいいよ」と言ってしまいました。
父母を一挙に半年の間に亡くしてしまったのです。それだけでも、僕は落ち込んでしまっていたのに、僕の不幸はそれでは終わりませんでした。
母が帰らぬ人となって一ヵ月後、僕は真夜中、がっしゃんと言う瀬戸物が壊れるような音で目が覚めました。「どうしたんだろう?」と起き上がりかけた僕は、急に体を揺すられて、倒れてしまいました。最初何が起こったのかわかりませんでした。それから家ががたがた揺れているのに気がつきました。「地震だ!」と思ったとたん、体がすくんでしまいました。それでも何とか這って台所のテーブルの下に潜り込みました。その後、すごい揺れに見舞われたかと思うと、バサーっと大きな音がして、天井が崩れ、屋根が落ちてきました。幸いにもテーブルの下にもぐっていたので、僕は押しつぶされなくて済みました。地面の揺れが何分続いたのか分かりません。数十秒だったのかもしれません。でも、僕には永遠に続くように思われました。揺れがおさまったところで、テーブルから出ようと思うと、テーブルが瓦礫に覆われていて、出られそうもありません。瓦礫を押しのけようと渾身の力を振り絞って押すのですが、びくともしません。僕は焦り始めました。暗闇の狭い空間で、額の汗をぬぐいながら、何度も押してみました。しかし焦れば焦るほど、瓦礫の山は僕をあざ笑うように、微動だにしないのです。僕はだんだん力が入らなくなり、このまま死ぬのかなあと思い始めました。しかし、そのうち誰かが助けに来るかもしれない。体力を消耗しないほうが得策なのかもしれないと考え直しました。ジーッとしていると、オーストラリアから帰って起こった不幸な出来事が走馬灯のように思い出されました。つらいことばかりでした。死ぬなら死んでもいいなと思いました。息もだんだん苦しくなってきました。空気が少なくなってきたようで、意識がだんだん薄れていくようでした。その時、外でワンワンと吼える犬の鳴き声が聞こえたかと思うと、人声がしたように思いました。僕は救助隊が来たのだと気づくと、思い切り声を張り上げました。「助けてくれ~」
「助けてくれ~!」と3度叫んだときでしょうか。「おーい。ここに誰か埋っているようだぞ」と声がしました。それから、木材や瓦礫を取り除いていく音がしました。そして、太陽の光が一条の明かりとなって僕のいる空間に差し込んできた時、「僕は助かったんだ!」と思いました。それから僕は救助隊の人に体を引っ張られて、外に出ることができました。その後病院に運ばれましたが、たいした外傷はないということで、うちに帰されました。とはいえ、家は屋根が押しつぶれて、もう家の中に入ることもできない状態でした。心配をして携帯に電話してきてくれた和恵おばさんのうちに、しばらく厄介になれることになったのは不幸中の幸いでした。和恵おばさんのうちで晩御飯をもらい床につこうかと思っていた時、ニュースで聞いたというオーストラリアにいる日本人の友達から電話がかかってきました。
「ニュースで聞いてびっくりしたんだけど、田中のうちは大丈夫だったの?」
「いや、全然大丈夫じゃないよ。家が全壊して、僕は屋根の下敷きになったんだ。でも救助隊に無事救出されたんだけど。今晩は親戚のうちに泊めてもらっているんだけど、これからどうしようかと思っているところだよ。本当にオーストラリアから帰ってから、父が自殺するし母は胃癌で苦しんで死ぬし、今度は地震で家が全壊だよ。僕は命こそ失わなかったけれど、次から次へと悪いことばかり起こって、心身ともにクタクタだよ。生きていくのもいやになったよ。まるで、誰かの呪いにかかったみたいだよ」
僕の使った呪いと言う言葉が引き金になって、その友達が言った言葉は、僕をぞっとさせました。
「呪いなんて、今の時代そんなことあるわけないだろ。そういえばつい最近ウルルの石を盗んで帰った連中が、いろんな不幸に見舞われるという記事が新聞に載っていたな。まさかウルルの石を盗んで帰ったんじゃないだろうな」
その友人はきっと冗談のつもりで言ったのでしょう。でも、僕は自分の顔の青くなっていくのが分かりました。
「そんなことがあるのか?」
「いやあ、新聞にはそう書いてあったけど。その連中が後悔して送り返した石と言うのを展示した所が、アリススプリングにはあるそうだよ」
僕は、疲れていたはずなのに、その晩は一睡もできませんでした。
そして翌朝早く、全壊した自宅に戻って行き、瓦礫の山をひっくり返していきました。そしたら、あったのです。ウルルの石が。僕はすぐに郵便局に行って、その石に謝罪文をつけてウルルの管理事務所に送り返しました。だから、ウルルの石のその展示場には今では僕の送り返した石も展示されていることでしょう。僕の謝罪文をつけて。
ウルルの石を送り返した翌日のことでした。これからどうして暮らしていこうかと浮かない思いで新聞を読んでいると、「自分史募集」の広告が目に留まりました。懸賞金3百万円。懸賞金の額も魅力的だったし、僕にこの一年間降りかかった不幸を書くことによって自分の気持ちの整理もできるように思い、それから日夜コンピュータに向かって、自分史を書き始めました。たとえ懸賞金がもらえなくっても、僕は今までの一生で、本当にやりたいことができ、心の底から湧き出る喜びを感じています。
次回 「ウルルの石 第三話 レイチェル・アンダーソンの話」にご期待ください。
著作権所有者・久保田満里子





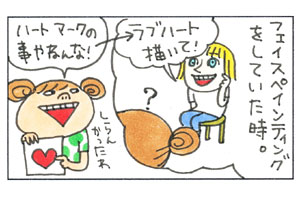
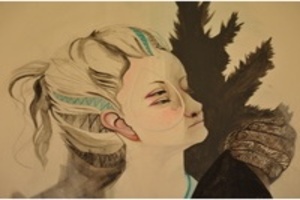





コメント