行方不明(6)
更新日: 2010-01-18
トニーがいなくなってからの1週間は、今から思えば、静子にとって希望と絶望の谷間を行き来していた毎日だった。電話が鳴る度に、警察からの朗報が届いたのかと飛び上がって出て、それが間違い電話とかセールスの電話だと、かっとなって受話器をたたきつけるようにして切ったものだ。姑とは事件後毎日電話で連絡を取っているが、姑は事件以来急に老け込んだように思えた。トニーは一人息子だったから無理もない。
2週間目になると、静子はトニーが生きて帰ってくる可能性が少なくなったことに不安を感じた。それと同時にトニーがいなくなって初めて、いかに彼に頼っていたかを切実に感じるようになった。電話代、電気代、ガス代等の請求書が来ても、全部トニーが処理してくれていたので途方に暮れた。その間、時々顔を覗けては、静子を慰めてくれたりアドバイスをしてくれたのはジョンだった。
そうこうしているうちに、1か月経ってしまった。
そんなおり、トニーの会社から、静子宛に手紙が届いた。それには、トニーの年休と病気休暇を合わせてトニーの不在をカバーして来たが、それも1ヶ月もたつと全部使い切ったことになり、これ以上給料の支払いは出来ないので解雇すると書かれていた。「こんなの、ひどい!」と、読んだなり、その場にへなへなと座り込んでしまった。トニーが行方不明になった翌日トニーの上司のギルバートと話した時、ギルバートが親身になってトニーの身を心配してくれていると信じていたので、解雇状を受け取った今、ギルバートに裏切られた気がした。しかし、嘆いていても事態が好転するわけではない。気を取り直して、姑に電話してこのことを伝え、アドバイスをもらおうと思ったが姑は悲観的だった。
「今はどこの会社も不景気だから、仕方ないんだろうね。私の友達の息子さんなんて、ある日会社に行ったら、上司から『机を片付けて会社の車のキーを返せ。2週間分の給料は銀行振込をするから、今日限り会社に来なくてもいい』って言われたそうだよ。オーストラリアの会社なんて、皆そんなものなんだよ」と溜息をつきながら言った。
静子は、悲しみにばかり浸っておれなくなった。生活の手段と言う問題が切実になって来ていた。メルボルン郊外にあるベッドルーム二つあるこのアパートだって、月1500ドル(10万円)する。このままでは 貯金だって半年で底をついてしまう。
それからは、水曜日と土曜日の新聞の求人広告にくまなく目を通した。英語がままにならない静子にできる仕事というのは限られていた。ウエートレスとか、皿洗いとか、掃除婦とか。その他には日本人の観光客相手の店員とか、ツアーガイドとかもできるかもしれない。ウエートレスとか皿洗いなんて、日本にいる両親に言ったら、何のために大学に行ったんだとなじられるだろうなと思いながら、新聞の求人欄を眺めた。幸いにも日本人相手の新聞の求人欄で見つけたツアーガイドの面接試験にパスして、何とかツアーガイドとして雇ってもらうことになった。時給はよかったがパートの仕事なので、収入の安定と言う面から不安があった。しかし、今は仕事の選り好みをしていられる状態ではなかった。会社から渡された観光案内の情報を頭に叩き込むのに、一週間かかった。旅行代理店に勤めていたおかげで顧客用語に悩まされなくて済んだのがせめてもの幸いであった。
ツアーの担当をしている木村さんから電話がかかってくると、空港に日本人の観光客を迎えにいく。「00ツアーの皆様」と書いた紙を掲げて客を待つのだが、時には飛行機が遅れて2、3時間空港で待たされることもあった。市内観光に行くときは、1847年に建てられた昔の金持ちの住んでいた豪邸「コモハウス」とか、戦死者を祭った「慰霊堂」、街中にある「フィッツロイガーデン」を案内するのだが、初めてバスに乗った時、マイクもろくに使えなくて、「聞こえません」と、後ろの席に座っていたお客さんに文句を言われたものだ。しかし一ヶ月もすると気持ちにゆとりができ、名所をよどみなく、また冗談を交えながら説明できるようになった。市内観光に慣れてくると、静子が担当する範囲が広がって、フィリップ島のペンギン観光や、バララットの金鉱にも行くようになった。バララットのソブリン・ヒルは1850年代、金鉱の町として栄えた。今は金鉱はもう廃鉱になっているのだが、昔の金鉱の様子を再現して観光地として有名になっている。しかし静子が一番好きなのはペンギンツアーだった。ペンギンのいるフィリップ島に行くには、バスで2時間ばかりかかるが、ツアーの夕食で出る伊勢エビは静子の好物だったし、日が暮れて集団になって小さな妖精ペンギンがよちよち歩きで浜をあがってくる様を見るのは、何度見ても愛らしく、心が和んだ。ただ夏時間が始まると、ペンギンが出てき始めるのは午後9時頃となり、それからまた市内にお客さんを送って行き、家に帰ると午前様になる。そんな日は、ベッドに潜り込むと昼間の緊張感から解放されて、どっと疲れを感じてしまう静子だった。
時には意地悪い客に悩まされることがあるものの、静子はガイドの仕事ができることに感謝していた。仕事は、大切な収入源になっただけではなく、静子に生きがいをを与えてくれたからだ。それにもまして、忙しさがだんだんとトニーのことに張り付いていた意識を剥がしていってくれたのは、幸いであった。
次回に続く.....
著作権所有者・久保田満里子








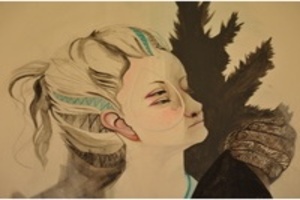



コメント