恐怖の一週間(2)
更新日: 2024-08-17
「え、オーストラリアに行くの?」と母は驚いて聞き返した。「うん。オーストラリアで働きながら、旅行をしてくるわ」
「あんたって、どうして衝動的にしかものを考えることができないの。お父さんそっくりね」と、母は愚痴っぽく言って部屋を出て行った。
ひょうたんからでたこまというのは、このことを言うのだろうか。それから私は俄然エネルギッシュになって、オーストラリア行きの準備をし始めた。そして私はオーストラリアに来た。19年前のことだった。ワーキングホリデーで、メルボルンのお土産物屋でアルバイトをしているときに、日本語の話せるオーストラリア人の店員仲間、ダンと知り合い、ダンと結婚して、メルボルンに住み着いた。
私はそんな昔のことを思い出しながら、ベッドから降りようとして、布団カバーを見て、ぎょっとなった。布団の足元のほうに5センチくらいの大きなしみがあったのだ。それは、まるで血が滴り落ちてついたような赤とも茶色ともいえないようなしみだった。それを見たとき、背筋がぞくっとした。今さっき見た夢とその血が合い重なって、私は恐怖で顔が引きつった。まるで、水子になった私と木村の子が、私を恨んで血を流したように思えた。私はそれでも、何とかそのしみを理性的に考える心のゆとりをとり戻し、愛猫のミーちゃんが、けがでもしたのではないかと思い直した。子供のいない私たちの飼っている三毛猫のミーちゃんは、私たちのベッドの上で寝る習慣がある。もしかしたら、ミーちゃんがけがでもしていて、血を流したのかもしれない。
「ミーちゃん、ミーちゃん」と呼ぶと、いつもは知らんぷりのミーちゃんはおなかをすかせていたようで、私の足元に擦り寄ってきた。私はミーちゃんを抱きかかえると、どこか怪我をしていないかと、背中から首もとを撫ぜて見た。しかし、やんわりとした毛が手に触れるだけで、どこにも傷跡はなかった。そして今度は仰向けに寝かせて、おなかも、おしりも調べて見た。ミーちゃんは抵抗もしないで、ごろにゃあと鳴きながら、気持ちよさそうに私に体を撫ぜさせた。体中何度も触って調べたが、怪我をしていなかった。その事実を確かめると、私はまた恐ろしさに身がすくんだ。
「やっぱり、この血は、おろされたあの子の血なんだ」
私は恐怖で、「きゃあ」と叫ぶと、ベッドルームから飛び出した。
「よしこ、冷静になれ、冷静になれ」
台所に行った私は、何度も自分に言い聞かせながら、うろうろ歩き回った。
ちょs







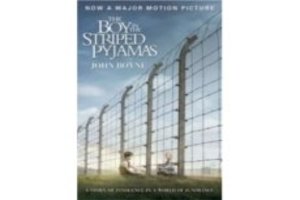




コメント