ピアノ熱(2)
更新日: 2024-12-07
文子は初めてのレッスンをうけるため、スティーブの家の前に立った時は、それまでの熱が少し冷めて理性を取り戻したようで、ピアノなんて自分に弾けるのかしらと自信がもてなくなってきた。しかし、「ハーイ」と笑顔で迎え入れてくれたスティーブを見ると、「よし、ものにしてやる」とファイトが湧いてきた。ピアノの前にすわると、スティーブが楽譜を出してきて、
「君、楽譜、読める?」と聞いてきた。楽譜なんて、高校の音楽の時間に見て以来、ご縁がなかった。
「まあ、簡単なのは」と言うと、おたまじゃくしが行儀良く並んでいる楽譜を目に前に置いてくれた。
「これはドで、この指でここを叩くとドの音がでます」
スティーブの手が文子の手を優しく包んだとき、文子は胸がドッキリとした。
それにスティーブの頬が文子の頬に近づいた時、自分の胸の高鳴りをスティーブに悟らせないようにするのに夢中で、その日のレッスンは、一体何を習ったのか覚えがないほど、文子は舞い上がっていた。
1時間のレッスンがすみ、家に帰るとすぐにピアノの前に座り、
「それじゃあ、これを来週までに練習しておいてください」と言われた箇所を夜遅くまで練習した。
その日の週末、明子から冷やかしの電話があった。
「初めてのレッスン、どうだった?続きそう?」
「頑張るわ」
それからの文子ときたら、友達からのランチの誘いも断ってピアノの練習に専念するようになった。スティーブから、「随分上達しましたねえ」と言われるのが、何よりの楽しみになったのだ。25歳で習い始めたピアノが、たいして物にならないことは文子でも分かっていたが、スティーブにほめられたい一心で練習に励んだ。そのうち、自分はスティーブが好きだからこんなに一生懸命になるのだろうと気がついた。スティーブが結婚しているかどうか分からないけれど、あれだけのハンサムな男だ。きっとガールフレンドくらいはいるだろうと想像した。でも、スティーブの家にはそれらしき写真は見当たらなかった。だから、ある日思い切ってデートに誘った。
「今度、うちに来ませんか?夕食をご馳走したいんです」
そうすると、スティーブは顔をほころばせて
「日本料理を作ってくれるの?ぼく、日本料理が大好きなんだ」と、すぐにデートに応じてくれた。文子は断られるのを覚悟していたので、スティーブの承諾は意外だった。
著作権所有者:久保田満里子




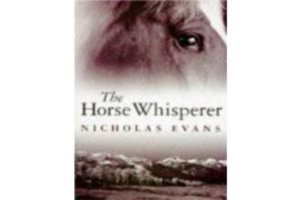








コメント