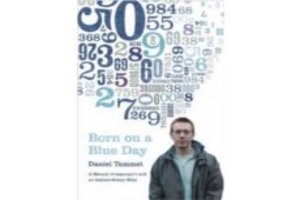私のソウルメイト(57)
更新日: 2012-12-02
「今朝中国側から社長が工場で首を吊って自殺したと連絡があったよ。全くひどいことになったもんだよ。だから、僕は明日は銀行の貸付の責任者とシドニーで会議があるので、明日一番の飛行機でシドニーに行くことになったよ」と答えた。
ロビンはその晩口数も少なく、翌日のその会議の書類の作成に追われていた。その日はさすがの私も彼に抱きつくような雰囲気でないのを感じて、彼の邪魔をしないように努めた。
翌朝五時半に起きてシャワーを浴びると、ロビンは朝ごはんも食べずに六時に家を出た。
その日は私も会社の行方が心配で、落ち着かない気持ちでどこにも出かけず、家にいた。
その夕方六時ごろ、玄関のベルが鳴り、インターフォンで顔を見ると、警官の制服を着た中年の男と、若い女が立っていた。
ドアを開けると
「ロビン・グーレイさんのお宅ですね?」と聞かれた。
「ええ、そうですが…」
「私は、ビクトリア警察署の巡査部長、ルーク・ファーガソンで、こちらは巡査のレベッカ・クーパーです」と、警察手帳を見せながら、中年の男は自己紹介をした。「ちょっと、お話があるのですが、中に入らせていただけませんか?」
「ここでは、だめですか?」
警官の制服を着て、警察手帳を持っているとはいえ、強盗が警官の制服を着ていることだってある。警察手帳となると初めて見るのだから、本物かどうか、その識別だってできない。私は、二人を家の中に入れるのはためらわれた。
「重大なお話なので、うちの中でお話したいのですが」と、中年の男が言い張るので、仕方なく二人を家の中に入れ、客間のソファーに座らせた。
「コーヒーでもいれましょうか」と言う私に
「いえ、結構です。それよりも奥さん、座ってください」と言う。
そこで初めてロビンに何か異変が起こったのではないかと胸騒ぎがし始めた。私はソファーに腰を下ろして
「ロビンに、何かあったのでしょうか?」と不安な気持ちに駆られて聞いた。
「ご主人は今日飛行機でシドニーから帰っていらっしゃる予定ですよね?」
「ええ、そうですが、それがなにか?」
「実は、今さっき飛行機が墜落したということで救急車や消防隊がかけつけたのですが、生存者がいませんでした。航空会社の方で乗客の名簿を調べたら、ご主人もその飛行機に乗っていらっしゃったことが分かりました」
頭をガーンと殴られたような気がした。
「そんな!」と言うと絶句してしまった。
「それで、死体を収容してある場所に来て頂いて、ご主人かどうか確認していただきたいのですが」と言う。
呆然としてしばらく口が利けなかった私を気の毒そうに見ながら、警官達は辛抱強く私の次の言葉を待っていた。私は心の中で、「ロビンが私の人生から消えてしまうことなんてありえない。信じられない」と繰り返し言っていた。
気がつくと、目の前に水の入ったグラスがあった。
「水でも、お飲みになったらいかがですか」
レベッカと言う警官が台所で水を入れてきてくれたらしい。私は黙ってグラスを受け取ると、ガプガプと飲んだ。
そしてのろのろソファーから立ち上がって、
「ちょっとハンドバッグを取って来ますから」と警官に断って、寝室に行って、財布の入っているハンドバックを手に持った。
それから、どんなことをしたのか、夢の中の出来事のようで、はっきりとは思い出せない。警官に連れられて、死体収容所に行ったが、そこは喧騒に包まれていた。顔の区別のできなくなった焼死体、手がもげてしまっている死体。どれを見ても事故の凄まじさを物語っていた。警官はその死体の一つに私を案内して、「この人の持ち物からロビン・グーレイさんだと思うのですが、確認していただけますか?」と言った。顔や手足が真っ黒にこげていたが、ロビンだと分かった。指に、私があげた結婚指輪をつけていたからだ。私は「ええ、夫です」と言うと、ロビンの変わりはてた姿にショックを受け、その場にへなへなと座り込んでしまった。警官は私を抱きかかえるようにして、二人で車でうちまで送ってくれた。
「遺体は、検死が済み次第、お返しします。多分二日後になると思われます」と言われた。
家に帰ると私は暗くなった部屋で、電気もつけずに座り込んでいた。
そこに一時間座っていたのか、二時間座っていたのか、あるいは十分しか座っていなかったのか定かではないが、電話の呼び鈴にはっとして、あわてて電気をつけて、電話に出た。
ダイアナだった。「ママ、今ニュースで見たわ。犠牲者の名前にロビンの名前が載っていたけど、まさかママのロビンではないでしょうね」
私は、ゆっくりと「ママのロビンはね、死んじゃったのよ」と答えた。その時初めてロビンの死が実感となって胸に迫り、涙がぽろぽろこぼれ始めた。
電話の向こうで、ダイアナが驚きで声を失っている気配がした。しばらくして、「ママ、今からそちらに行くわ」と言うと電話のガチャンと切れる音がした。
その晩は、ダイアナが心配して家に泊まってくれた。私は魂を失ったロボットのようになっていたからだ。
著作権所有者:久保田満里子