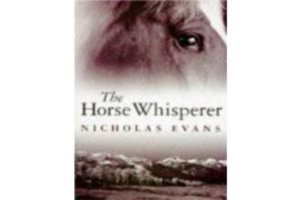透明人間(1)
更新日: 2016-06-05
朝、目覚まし時計の音で起こされた里香は、隣に寝ている夫のスコットのほうを見て、びっくり仰天して、ベッドから転がり落ちてしまった。落ちた時に、肩をベッドサイドテーブルの角でぶつけ、余りの痛さに「いたたた!」と言いながら、肩をさすった。すると、「大丈夫か?」と夫の声が聞こえ、声がするほうを見ると、誰もいない。里香がびっくりした原因は、夫の側の布団は夫の体で盛り上がって見えるのに、頭がなかったからである。おっかなびっくり、「スコット、そこにいるの?」とささやくように聞く里香に、「変なことを言うなよ。勿論僕はここにいるじゃないか」ととりたてて慌てた様子もない夫の声が返ってくる。そろりそろりとスコットの声のするほうに手を伸ばしすと、スコットの毛深い腕の感触が手に伝わってきた。でも、見えない。
「もしかしたら、スコット、あなた透明人間になったの?」
里香の問いに、ケタケタとスコットの笑い声が聞こえた。
「僕が透明人間になったって?馬鹿なことを言うなよ」
そういうと布団がめくれたのだが、里香にはスコットの姿が見えない。どうやら布団から出たようなのだけは、分かる。
「スコット。あなた、本当に透明人間になったみたいよ。私にはあなたの姿がちっとも見えないんだもの。私の言うことを信じられないのだったら、自分で風呂場の鏡を見たら?」
それからしばらくすると、風呂場のほうからスコットの叫び声がした。
「Oh, No」
どうやらスコットも自分が透明人間になっていることに気がついたようである。
「僕の体、どうなっちゃったんだろう」
里香の頭も、混乱していて、スコットの質問には答えられない。
きのう、何か変なものを食べたんじゃないかしら等とつまらぬことを考えたが、きのうは、スコットはいつものように、里香と同じものを食べたから、食べ物が原因ではなさそうだ。何かの薬を飲んで透明人間になったという小説も読んだことがあるような気がするが、スコットは夕べ変な薬も飲んではいない。
「どうすれば、いいんだ」
そのスコットの質問に、里香は慌てふためいた。
「今日、そんな姿では、とてもじゃないけど、あなた、学校に行けないわよ」
スコットは高校で数学を教えているのだ。透明人間が学校に行けば、大騒ぎになるだけだ。
「今日は、ともかく休んで、様子をみましょうよ」
里香は、それくらいの提案しか出来なかった。何しろスコットの姿が見えないので、どこにいるのかも分からないのだが、風呂場で放心した状態でいるようだ。
「ともかく、あなたが裸でいたら、どこにいるのか分からないから、服だけでも着てよ」
そういうと、洋服ダンスの引き出しが、スーッと開く。そして、引き出しの中のパンツや靴下が出て来るのが見える。そして、パンツをはいているのか、パンツだけが宙に浮いて見える。そしてソックスがはかれる。パンツが宙に浮き、ソックスが床について見えるのが、なんとなく滑稽である。そして、ワイシャツが着られ、ズボンがはかれた。これで、どこにスコットがいるのかは分かる。しかし首から上と手が見えないのは、なんとも不気味である。
「スコット、すごく変だわ。何とか顔や手も見えればいいんだけれど。どうすればいいかしら」
そう言っているうちに、里香は透明人間って包帯を体中に巻きつけて、サングラスをかけているのを思いだした。あいにく家には包帯は置いていない。どうすればいいんだろうと考えていくうちに里香の頭にひらめくものがあった。里香は鏡台から自分の化粧道具を出すと、スコットに言った。
「ここに、座って、このファンデーションを顔に塗ってよ」と、ファンデーションを鏡台の上に置いた。
スコットが抗議をするのではないかという里香の思惑に反して、スコットは黙ってファンデーションを塗り始めた。するとまず、右の頬が現れた。そして左の頬。鼻、おでこ、あご。どんどん塗られて、顔の輪郭ができあがっていく。やっとファンデーションを塗り終わった後で、里香は口紅を鏡台の上に置き、
「口紅もつけてよ」と里香が言うと、
「冗談じゃない」とスコットは抗議をしたが、確かに唇が透明なのは余り見られたものではない。しぶしぶスコットは、口紅をつけた。その後、里香の持っているかつらをかぶせると、女装したスコットになり、里香は思わず、ぷっと笑った。ただ目だけがまだ空洞となって、透明であるのが不気味である。スコットにサングラスをかけさせると、鼻が高いので、なかなかの美人に見える。最初のショック状態が収まると、次に心配になってきたのは、仕事のことである。
「まさか、お化粧して学校に行くわけには行かないでしょうから、今日は休んだほうがいいんじゃない」
スコットも、まさか化粧姿で、外出することは考えていなかったらしく、
「今日は休むよ」と、里香の提案に同意した。
そう決まると、すぐに「僕、今日頭が痛いので、休ませていただきます」とスコットは自分で学校に電話した。日本だったら、他の人に病欠の連絡を頼まないと、すぐに仮病だと分かるので、本人が電話することはないのだろうが、オーストラリアでは余り気にしないようだ。Sickyなんてずる休みをするときに使う用語まであり、日本の仮病という言葉のような後ろめたさがない。
著作権所有者:久保田満里子