EMR (16)
更新日: 2011-04-17
理沙は、もう一度「ジーンズ・オンリー」の店を見たが、誰も客が入る様子はなかった。それからマンションに帰った理沙は、疲れを感じ、ぐったりした。省吾のこと、テロリストのこと、今日は本当に神経が消耗することばかり起こった。今晩のテレビで、テロリスト逮捕のニュースが見られるだろうから、テロリストのことは警察に任せればいいんだと思いながらも、何だか落ち着かない気分だった。省吾は、時間が経てば元気になってくれるだろう。省吾に似合う女友達を彼に紹介した方がいいかなと思ったが、そんな女友達は、すぐには思い浮かばなかった。
のろのろマンションの中を片付けていると、六時になった。夕方のテレビニュースが見られる時間である。テレビのスイッチを入れると、理沙は緊張した面持ちで、テレビの画面を食い入るように見た。テロリストの話はトップニュースだろうから、最初に報道されるだろう。そう思っていると、
「フットボール選手のマシュー・ロングがパブで酔っ払い、パブにいた客を殴って軽症を負わせました。そのため、彼の所属するフットボールクラブは彼に罰金五千ドルを課し、五試合出場停止を命じました」と、マシュー・ロングの写真が大写しに出た。メルボルンで一番の大事件がフットボール選手の暴行事件とは、なんてメルボルンは平和な街なんだろうと、理沙は思わずにはいられなかった。
オーストラリア人のフットボールとクリケット熱は、日本人の野球やサッカー熱を上回ることを考えれば、仕方ないことなのかもしれないとは思った。では、次のニュースで出てくるのかなと思うと、次のニュースは、新資源税に労働組合も反対しているというニュースだった。理沙はじっとテレビを見たが、結局最後まで、テロリストの話は出てこなかった。やはり、警察では私たちの流した情報は真面目に受止められなかったのだろうか?そうとしか思えなかった。ニュース番組が終わるとすぐに、ハリーの携帯に電話した。
「ハリー、テレビのニュースを見たけれど、テロリスト逮捕の情報はなかったわ。私たちの流した情報を警察はまともにとってはくれなかったんじゃないかしら?」
「そんなことはないと思うけど。オーストラリア政府だって、アメリカに加担しているって言うので、イスラム教過激派からは敵視されているのを知っているはずだからね」
「じゃあ、どうして、あの男を捕まえなかったのかしら?」
「さあ、警察には警察の考えがあるんじゃないか?たとえば本当は逮捕したけれど、何らかの理由で極秘にしておくとか」
「それだったらいいんだけど・・。今朝あなたと別れた後、私、あの男を見張っていたけれど、逮捕されたようすはなかったわ。もっとも私が監視したのは昼過ぎまでだけど・」
「そんなに気になるなら、もう一度警察に電話してみるよ」
「そうお願いできれば嬉しいわ。警察に電話した後、何か情報が得られたら、私にも教えてもらえるかしら。こんな状態では、私、不安で眠れそうにもないわ」
「分かった。じゃあ、また電話するよ」
「お願いします」と、電話を切った後も、理沙の不安な気持ちはおさまるどころか、入道雲のように、ムクムクと膨れ上がっていった。
きっちり十分後に、ハリーから電話が来た。飛びつくようにして電話に出た理沙に、受話器を通して聞こえるハリーの声は沈んでいた。
「やっぱり、警察では僕達の言うことを信じていなかったようだよ。仕方ないからEMRのことを話したら、一度そのEMRを持って、警察本部に話に来てくれないかというんだよ。君に今から用事がなければ、二人で警察に行って、説明した方がいいと思うんだけど」
理沙は、今日は疲れたのでまた外出するのは気がすすまなかったが、事の重大性を考えると、疲れているからまたにしてとは言えなかった。決行の日は月曜日だということだから、もう3日もない。
「いいですよ。では、警察署で落ち合うということにしましょうか?」
「いや、僕は車を持っているから、車で君を迎えに行くよ。それから一緒に行ったほうがいいだろう。警察ではEMRを見てみたいということだから、EMRも持って行こう」
「じゃあ、待っています」
理沙が夕食の片づけを済ませた頃マンションに現われたハリーは、少々疲れているようだった。
「本当はEMRは完成したところで公表したかったのに、そうは言ってはいられなくなったな」と、警察署に向かう車の中で、残念そうに言った。
理沙はここで、謝るべきかどうか迷ったが、こんな事態になったのは自分の過失とは思えなかったので、黙っていた。
警察署本部に着いた時は完全に日は沈んでいたが、本部の前の蛍光灯が煌々とついていた。
建物の中に入ると中は深閑としており、受付に一人女性の警官がいた。ハリーがその警官に事情を説明すると、彼女はインターフォンで誰かを呼んだ。すると間もなく、四十代くらいの背の高いがっちりしたいかにもスポーツマンと言った感じの背広姿の男が、姿を現した。
「テロリスト対策本部の警部、マーク・クロフォードです」と、自己紹介をしながら、ハリーと握手をし、その後、ハリーのそばに立っていた理沙にも握手の手を差し伸べた。
「僕は、東オーストラリア大学の理学部のハリー・アンダーソン。こちらは、僕の研究協力者の林理沙さんです」と、ハリーが言うと、小さな取調べ室にマークは二人を招きいれた。
三人が腰をおろしたところで、マークがまず口を切った。
「最近ガセネタが多いので、信憑性のあるものから調査していくことにしていますので、お二人からの情報はまだ調査に乗り出していません」
「調査に乗り出していませんなんて、のんきなことをいっている場合ではないでしょ?決行は来週の月曜日なのですよ」
理沙は思わず大声でマークを怒鳴りつけるように言った。





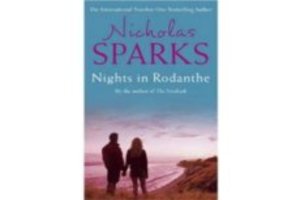






コメント