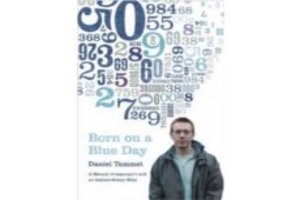百済の王子(16)
更新日: 2015-06-15
第四章:乙巳の変
その日、7月10日には、 豊璋は三韓進調の儀式をするから、宮殿に来るようにと、宮中から通達を受けていた。三韓進調と言うのは、朝鮮半島の三国、高句麗、百済、新羅が外交儀礼として貢物をする儀式のことである。 豊璋は、その儀式に参列するために、百済から取り寄せた贈り物を荷車に乗せさせ、蘇我蝦夷にもらった馬にまたがって、宮殿に向かった。雨がシトシト降り、宮殿へ行くまで、馬は泥道に足をとられてはかどらず、いつもよりは時間がかかった。宮殿内にある大極殿に着くと、宮殿の外に立っていた兵士から
「ここから先は護衛無しでお願いします。また刀をお持ちでしたら、お預かりします」と言われ、刀を取られた上、供の者を残して、一人大極殿に入った。 豊璋は、新羅の善徳女王の使者のいる下座に案内され、その使者のそばで待つようにと言われた。新羅と百済は仇敵の中だ。どちらも今ある三国をまとめて朝鮮半島を統一したいと言う念願をもっている。倭国もそれを知っているが、倭国を百済からも新羅からも貢物をもらう大国であるということをみせつけるための儀式なのは明らかであった。前にも言ったように、新羅の善徳女王と 豊璋の祖母、善花王女は姉妹である。 豊璋の祖父、百済の武王は、美人の誉れ高かった善花王女に恋して善花の父親の真平王の反対を押し切って結婚したと言う。政略結婚が普通だった王室としては珍しいケースだった。しかし、そのために 豊璋の父、義慈王は、母親が敵国の者だというので、百済の豪族から即位を阻められ、随分苦労したことは、誰もが知っていることであった。だから、新羅の王家に対して血縁だからと言って親近感をもつことはなかった。三韓進調と言っても高句麗の使者は見当たらなかった。今の実権を握っている蘇我入鹿の姿もまだ見当たらなかった。皇極天皇が出ていらっしゃるのを待っいると、後ろから肩を叩かれた。振り返ると、いつの間にか蘇我入鹿が入ってきて豊璋の後ろに立っていた。
「 豊璋殿も、呼び出されましたか?なんともや、新羅の使者への謁見に 豊璋殿まで呼び出すなんて、天皇もお人が悪いですな」と言って、ウワハッハと豪快に笑った。おおっぴらに天皇の悪口を言うなんて恐れ多いことができるのは、この国では蘇我入鹿しかいない。
「 豊璋どの。これは大きな声では言えませんがな、最近他国からの使者が貢物を持ってきた時にわざわざ天皇がお会いになると言うことはありませなんだ。全て私に任されていたのが、今回はわざわざお会いになるという。おかしいとは思いませんか。百済にとって憂慮するべきことかもしれませんなあ」と言った。
「でも、私が来た時も天皇にお会いしましたよ」
「いやあ、一国の王子が来たときは、ただの使者が来た時とは違いますよ」と蘇我入鹿は 豊璋の気持ちをさか撫ぜるようなことを言った。
『確かにそうかもしれない。これは倭国と新羅が手を結ぶということだろうか?』と 豊璋は不安な気持ちに陥った。
朝廷の有力な豪族たちもそろい、皇極天皇がおでましになり、天皇の側には古人大兄皇子が控えた。古人大兄皇子は、皇極天皇の夫だった舒明天皇が、蘇我蝦夷の妹に産ませた子だ。皇極天皇の後継者として、うわさされているのを 豊璋もきいたことがある。天皇が玉座につかれると、まず、新羅の使者が皇極天皇に挨拶をし、善徳女王から預かっていた上表文を朗々と読み上げた。そのあと、倉山田の臣(おみ)麻呂が、新羅の貢物の目録を読み上げ始めた。ところが、途中から読み進んでいた麻呂の声が震え始めた。どうしたのかと麻呂を見ると、顔に汗が吹き出ている。そのうち目録を持っている手までも震え始め、どうしたのかといぶかっていると、蘇我入鹿も、麻呂の態度に不審を抱いたようで、麻呂に向かって、「なぜ震えているのか?」と聞いた。麻呂は一瞬息を飲み込んだが、「天皇のお側近くにおりますのがおそれおおくて、不覚にも汗をかきました」と答えた。すると、その言葉が終わるか終わらないかと言うとき、「やあ」と大きな掛け声が宮殿内に響き渡った。
著作権所有者 久保田満里子