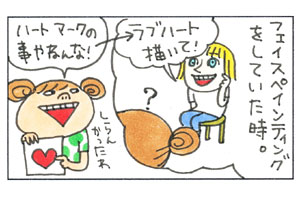ケリーの母(4)
更新日: 2016-04-10
誠が言っていたように、晩御飯の時間になって、ビルが来た。ビルの奥さんは3年前に亡くなったそうで、二人いる子供たちは広島に出てしまい、今は一人暮らしだと言う。
晩御飯に出たすき焼きを食べ終わると、清子は早めに寝てしまい、恵も食事の後片付けでいなくなり、ケリーとビルと誠三人が客間に残された。それまでは誠が通訳をしなければならなかったので、会話も途絶えがちだったのだが、三人は英語に切り替えて、話し始めた。
「いやあ、今だから言えるけど、僕も実は美佐子さんには目をつけていたんだよ。明るくて、頭が良くて、進駐軍の食堂では、人気者だったんだよ。ジェラルドが、彼女をデートに誘って成功したと聞いた時は、悔しかったものだ」
お酒が回ってきたのか、ビルは饒舌になった。
「ジェラルドとは、1946年に一緒に呉に来たんだよ。進駐軍として日本に行く兵士の公募があってね。その時、仕事にあぶれていたし、オーストラリア人の捕虜に対する日本軍の残酷な仕打ちに仕返しをしてやりたいという気持ちもあって、応募したんだ。
ジェラルドも同じような気持ちだったらしい。ニップ(ジャップよりもっと軽蔑の意味をこめた日本人を表す言葉)に思いしらせてやるという気持ちで来たんだけれど、呉の沖合いに沈没した戦艦を見たとき、戦争の悲惨さを見せ付けられた気がしたよ。さび付いた船が傾いて上体だけが見えたんだ。呉に上陸した時、出迎えた日本人たちは、皆空虚な目をしていたよ。笑いもせず、泣きもせず、まるでお面のような何の感情ももたない目をしていた。誰一人話す人もなく、しーんとしていたことも不気味だったな」
「何人くらい、呉に来たんですか?」と誠が聞いた。
「多い時は1万2千人いたよ。僕たちに最初に与えられた仕事は広島の原爆跡の調査だったが、あの光景を見て、それまでの仕返しをしたやりたいという気持ちは吹き飛んだよ。原爆で焼け爛れた人たち、あちこちに転がっている人間とは思えない焼けた肉の塊になったような死骸の山。その死骸のにおいがすごいんだ。あの時、たとえどんな敵であったにしても、原爆だけは落とすべきではなかったと、つくづく思ったよ」
ケリーは、母親から余り戦争の話を聞いたことがなかったので、ビルの話には衝撃を受けた。
「僕たち進駐軍の使命は、日本を民主化することだったんだけど、日本人と個人的につきあわないようにと厳しく言われていたんだ。日本人の家に入ってはいけない。日本人と個人的につきあってはいけない。映画館やダンスホール、バーなどでも日本人と交わってはいけないと命令がだされていたんだ。けれど、それは無理な話っていうものだよな。お互い人間なんだから。それに個人的に接しないで、日本人に民主主義を教えろというのは、無茶な話だよな。あの頃進駐軍には1万人から2万人もの日本人が雇われていたんだ。毎日顔を合わせていれば、情もわくというもんだよ。僕も結局は美佐ちゃんには振られちゃったけど、文子と言う、ウエイトレスとして働いていた子と、付き合って結婚したんだよ。もっとも、オーストラリアでは、敵国との女との結婚は許されていなかったから、皆日本式の結婚式をあげる以外なかったんだけれど。1951年に日本と平和条約が結ばれると僕たちの役目は終わったって言うんで、1952年には皆オーストラリアに引き揚げてしまったけれど、僕は結局日本にいついたんだよ」
「なぜ、オーストラリアに帰らなかったんですか?」
「もうその頃息子もいたからね。オーストラリアではまだ日本に対して恨みを持つ人たちも多かったから、文子や息子にはオーストラリアは住みにくい所だと思ったんだよ」
「オーストラリアに帰らなかったことを後悔しませんでしたか?」
ケリーは、思わず聞いてしまった。
「後悔?していないよ。英語教師をしたり、通訳をして、結構収入も良かったし、白人と言うことで、ちやほやされるところもあったし、居心地がよかったよ」
それを聞くと、思わずケリーは、父親があのまま日本にいることを決意していたら、僕たちの家族は崩壊してしまわなかったのだろうかと、ふと思った。
「そういえば、一度オーストラリアのチーフリー首相が呉に慰問に訪れたことがあるんだ。その頃、性病にかかる兵隊が多くて、一年で4500人は性病にかかったそうだ。チーフリーが僕たちを前にして、日本人の女との結婚は禁じる。白豪主義政策を今まで以上に厳しくして、日本人の女は一人たりともオーストラリアには入国させないと、息巻いていたよ」
ケリーは父母がそんな困難な状況に反して結婚したのかと、改めて父母の情熱が思い起こされた。
「ところで、ジェラルドは、今何をしているんだ?」ビルが思い出したように聞いた。
「知りません」
「知らない?」
「ええ、母が亡くなる前に父を探し出して連絡しようかと思いましたが、母からそんなことをするなと言われ、結局母は父と別れて一度も会わずに死んでしまいました」
「そうだったのか。それじゃあ、僕のほうが君よりジェラルドのことはくわしいかもしれないな」
「最後に父と連絡をとったのはいつでしたか?」
「5年前だったな。クリスマスカードが来たよ」
「父は何をしていたのでしょうか?」
「タクシーの運転手を長いことしていたが、65歳で退職して、年金暮らしのはずだよ。そういえば、普通従軍すれば普通の人よりはたくさん年金がもらえるはずなのだが、日本に駐屯していた兵隊は長い間従軍したとは認められないで、それを認めさせるために随分運動をしたようだったよ」
「そうですか。その時は、どこに住んでいましたか?」
「ジーロングに住んでいたよ」
ジーロングといえば、メルボルンから75キロ離れた人口22万人のビクトリア州第二の都市だ。
「父は再婚したのでしょうか?」
「そうだよ。そういえば、君には10歳違いの腹違いの妹がいるはずだ」
腹違いの妹がいるといわれても、ケリーにはピンとこなかった。
「最後のクリスマスカードには君が有名な学者になって鼻が高いと書いてあったよ」
それには、ケリーは驚かされた。もう自分のことなどすっかり忘れているだろうと思っていたからだ。
「僕のことを覚えていたんですか」
今度はビルのほうが驚いた顔をして、
「勿論だよ。君のことが新聞に載るたびに、その記事を切り抜いていると言っていたよ。君は彼の自慢の息子だったよ。実は君に見せようと思って、ジェラルドから来たクリスマスカードを持ってきたよ」と、ビルがポケットから取り出したクリスマスカードは、10枚5ドルで買える、クリスマスツリーが描いてある安物のカードだった。そこには、
「ビル、クリスマスおめでとう。
今年で82歳になった。去年シェリーが亡くなって一人になってしまったが、今でも自分の家に一人で住んでいる。娘のレオーニーはメルボルンに住んでいて、時々様子を見に来てくれる。息子のケリーのことは、君も覚えているかもしれないが、あのやんちゃ坊主が今ではノーベル賞候補にのぼっていると先日新聞で読んだ。親として鼻が高いよ。
では、元気で。 ジェラルド」
簡単な文だったが、自分の名前が書いてあるカードを見ると、ケリーは、一度父親に会ってみたいという気持ちがわいてきた。母が生きているときは、たまに会ってみたいと思うことはあったが、会うなんてことは母を裏切るような気がして、会えなかったのだ。
「父の住所は、分かりますか?」
「今日は持ってこなかったよ。いつ帰るんだ?」
「明日の昼過ぎです」
「もう、明日帰るのか。じゃあ、明日の朝、持ってくるよ」
そういうと、ビルは帰ってしまった。
恵が敷いておいてくれた布団にもぐりこむと、ケリーはすぐに眠ってしまった。
参考文献
Neville Meaney (2007) towards a new vision: Australia and Japan across time. University of New South Wales Press Ltd.
Kelly Ryan (2010) True love triumphed for Digger Gordon Parker and his young wife Cherry.
Herald Sun May/25/2010
Momento: National Archives of Australian. Winter 06. Australian women in the British Commonwealth Occupation Force (1946-1952)
Walter Hamilton. Children of the Occupation: Japan’s untold story
著作権所有者:久保田満里子