アインシュタインの覚書(3)
更新日: 2023-01-28
佐藤修平は、茨城県の出身で、中学校を卒業した後、集団就職で東京に出てきて、帝国ホテルのボーイになった。まだ16歳の少年である。今日、有名な物理学者がホテルに泊まると聞いていたが、その偉い先生に届け物をする役がまわってきて、少し嬉しくなった。何しろノーベル賞をもらったえらい先生だと言うので、多くの日本人が彼を一目見ようと沿道に押し掛けたことは、ほかのホテルの従業員から聞いていた。その人物に会えるチャンスができたのだ。部屋の前まで行ったが、さすがにドアをノックする前は緊張して、かすれそうになる喉を潤すために唾をのみ込んだ。
ドアをノックして、「お届け物です」と言うとすぐに「どうぞ」と男の声が部屋の中から聞こえ、ドアが開けられた。ドアの向こうには、おちゃめな感じの白髪をオールバックにした老人が立っていた。
「お届物を持ってまいりました」
届け物を受け取るとアインシュタインは、自分のポケットをまさぐった。ポケットには思ったものがなかったようで、
「チップをあげようと思ったんだが、残念ながら日本の小銭を持っていないんだ。これをチップ代わりにあげるよ」と言って、ホテルの名前の入ったメモ用紙を二枚手渡された。修平は、アルファベット語で走り書きしてあるそのメモ用紙の内容はさっぱり分からない。戸惑っていると、アインシュタインは、「これは、今私が書いたものだけれど、うまくすれば、チップ以上の値打ちが出るかもしれんよ」と、ウインクしながら言った。
修平は、そのメモ用紙を大事にポケットにしまうと、「ありがとうございます」と言って部屋を出て行った。
修平は、何となくアインシュタインからメモ用紙をもらったことを同僚に言いにくくて黙っていた。何しろ有名人の部屋に行ったと言うので、同僚からうらやましがられていたので、これ以上同僚のやっかみを買うのは御免蒙りたい気分だったからだ。
家に帰ると、そのメモ用紙を取り出し、そのメモ用紙は箱に入れて、大切に押し入れにしまった。
修平はその後結婚したが、子供はできなかった。妻はよく気の付く優しい女で、子供がいなくてもそれなりに幸せな人生を送り、1962年、肺がんを患ってこの世を去った。アインシュタインからもらったメモ用紙は、修平の死んだあとそのまま忘れ去られ、長い間押し入れの奥に眠ったままになっていた。
ちょさく









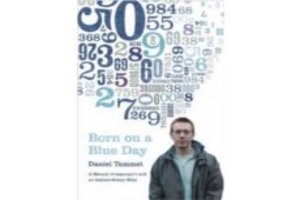



コメント